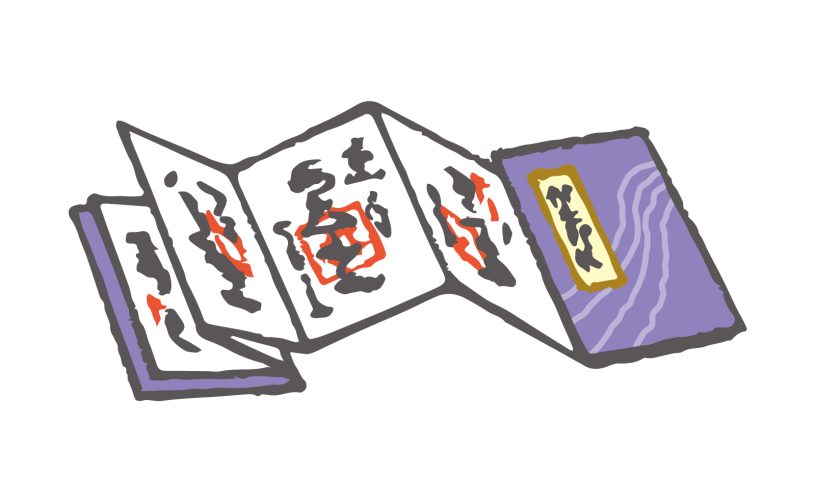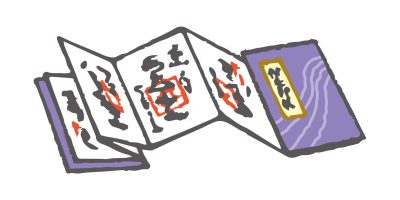私たちは街歩きでいろいろな寺院を訪ねてきました。仏教では成仏(仏になること)が最終目標であると理解しています。成仏とは、死ぬことと悟ることの二つの意味があります。日本では、死ぬと仏になる、と表現します。それとは別に、本来の仏(悟った人の意味)になるため(禅宗を中心として)修行して悟る、という意味もあります。
ということで、私たちは死ぬと仏になれるようではありますが(多分)、生きている間に悟ることはできるのか、というのがここで書きたいことです。はっきり言って、日々の生活で欲にまみれた私達には悟りなんてとても難しそうですが、私たちには悟りにほぼ匹敵する重要なことがあるのではないか、という視点で考えます。
私たちが若者だった頃「青年は荒野をめざす」を歌いました。今は「老人は悟りをめざす」を謳います。
なお、この記事とほぼ同じ内容を、別ブログの「私達も悟ることはできるか」という記事に書いてあります。
悟りのランク
それでは、私達にとって悟りとはどのようなことが想定されるか考えてみましょう。今、高齢で怒りっぽくなった人(私のような普通の後期高齢者)の例を取り上げます。以下のように整理できるでしょうか。
1.何かというと怒りの感情に襲われる衆生の私のままでよい
→ 私が怒りっぽいのは私のキャラだからこれでいいのだ、と悟る
2.少し努力して怒りを抑えられ不安やストレスの少ない私になりたい
→ 最終的な「悟り」は望まないものの、少し心に余裕を持つ
3.厳しい修行をして最終的な悟りに至った私になりたい
→ 悟った、枯れた、理想的な?老人になる
こう書いてみると、努力が多ければ得られるご利益は大きく、少ない努力では少ない成果しか得られない。ということのようです。従って、費用対効果という観点では最適なランクを決めるのは難しそうで、結局、私たちがそれぞれ、何を狙うか、という目的意識が決め手のようです。
仏教の悟りとはどういうことか
それでは、悟りとは何でしょうか。いろいろと定義はありそうでしたので、悟りについて別のブログに「仏教の「悟り」とはどういうことか」という記事を書きました。ここでは要点だけ書きます。
悟りというと禅宗の修行を思い浮かべます。しかし、私には禅宗の知識がありませんので、初期仏教の悟りについてまとめると、以下のようなことかと思います。
釈迦は、悟りとは「苦」から開放され、安寧の状態になることだと捉えました。釈迦は、絶対的な(永遠に続く)自己というものは無いのに(無常)、自己に執着するために苦しみが生まれるのだから、自己を捨て去れば、つまり、自己は存在しないことを会得できれば(無我)、そうすれば悟りに達する、と言っていたようです。そのための瞑想法をいろいろ考えたようです。しかし、当時、悟るためには瞑想を主体とする修行が重要で、すべてを捨てて出家せざるをえませんでした。つまり、日常の生活を送りながら悟ることは不可能でした。
「苦」とは何か
ここで少し「苦」について書いておきます。釈迦は、苦とは生老病死から生まれ、特に、物事が自分の思い通りにならないことだと説明しました。「苦」についても「仏教の「悟り」とはどういうことか」という記事に書いてありますので参照してください。
私たちの生活での苦しみとして、病や死といったことに加え、自分の思いとは異なる状態になることが、確かにあります。それは、不安に苛まれ、ストレスまみれになり、怒りの感情を抑えられないことなど様々です。
これらは、私たちにとってはかなり重要なことです。そう考えると、私達にとって、必ずしも悟りに至る必要はなくて、日常的な苦(意志に反した望まぬ状況)から開放されるならそれはそれで一つの重要な目標になるといえそうです。
つまり、ここでは、わたしたちの日常の悩みから逃れるため、一先ず、不安、ストレス、怒りの気持ち軽減できること、ネガティブな感情を減らすこととを私たちの目標にしましょう。これって、実は悟りにかなり近いかもしれません。
つまり、最初に書いた悟りのランクの2.を狙うことも適切かと思われます。
私達が使える瞑想法
さて、心をコントロールする手法が瞑想であり、禅やその他いろいろな手法があります。瞑想法については、「様々な瞑想法とそれらの特徴」というブログ記事にまとめました。そこでは、禅の瞑想の他に、リラクゼーション型の瞑想とマインドフルネスの瞑想を書きました。それぞれの瞑想の方法、特徴などはその記事を見ていただきたいのですが、結論だけ下に書いておきます。
上で書いたいずれの瞑想でも、共通するのは、気持ちを集中することが第一歩です。その先がそれぞれ異なります。
- 禅では、意識を集中しそれを究極まで高めます。
- リラクゼーション型では、意識を集中し心身をリラックスさせます。
- マインドフルネスでは、意識を集中し自分の思考の動きに気づけるようにします。
あなたはどこを狙うか
この記事の最初に、悟りのランクを書きました。仏教における瞑想は最終的な悟りを目指すようですが、日常生活を送りながら最終目標にいたるのは難しそうです。しかし、悟りのランク2.であれば、私達にも手の届く範囲にありそうです。
現在、心理学、脳科学の進歩によりその知見を使い、普通の人でも自分の心をある程度コントロールできるようになってきましたので、私達も、それなりに、悟りに近づくことができるかもしれません。