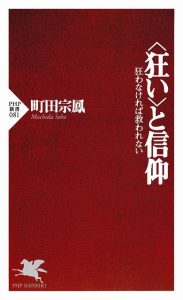私達凡人も悟ることはできるか
仏教の悟りというのはなかなか難しそうですが、ここでは、現在ある様々な瞑想法のどれかを利用し、日常生活をしながら、すこしでも悟りに近づくことはできないものか、ということを考えてみました。
悟りと言っても定義がよく分かりませんので、先ず、悟りについて少し調べ。次に、数ある瞑想法について少し整理してみます。そして、今の時代に即した悟りが何かということを考えてみます。
悟りのランク
私達は何を目指すべきかを考えてみましょう。今、高齢で怒りっぽくなった人(私のような普通の後期高齢者)の例を取り上げます。整理してみると、悟りのランクは次のような感じでしょうか。
1.何かというと怒りの感情に襲われる衆生の私のままでよい
→ 私が怒りっぽいのは私のキャラだからこれでいいのだ、と悟る
2.少し努力して怒りを抑えられストレスが軽減できる私になりたい
→ 最終的な「悟り」は望まないものの、少し心に余裕を持つ
3.厳しい修行をして最終的な悟りに至ることを目指したい
→ 悟った、枯れた、理想的な?老人になる
たくさん努力をすれば成果も大きく、少ない努力では少ない成果しか得られない。ということのようです。つまり、費用対効果の極小値がみつかりませんので、費用対効果という観点ではどれか一つを選び出すのは難しそうであり、結局、私たちがそれぞれ、何を狙うか、という目的意識次第のようです。
悟りの局地、仏教の悟りとは
それでは、悟りとは何でしょうか。いろいろな定義がありそうでしたので、悟りについて「仏教の「悟り」とはどういうことか」という記事を書きました。ここでは、以下に要約して書きます。
悟り、というと、仏教の悟りのことを思い浮かべます。そして、悟りについて述べているのは禅宗のお坊さん、というイメージです。ところで、悟り、とはどういう状態をいうのでしょうか。それを知りたいところですが、お坊さんによって表現が異なりますので、どの方の言葉を信じればよいのか分かりません。
初期仏教(釈迦が生きていた頃の仏教)での悟りについては、釈迦は、悟りとは「苦」から開放されることだと捉えました。釈迦は、絶対的な(永遠に続く)自己というものは無いのに、自己に執着するために苦しみが生まれるのだから、自己を捨て去れば、つまり、自己は存在しないことを会得できれば悟りに達する、と言っていたようです。仏教では、自己というものにこだわるかどうか、が悟りの境地と関係があるようです。しかし、悟るには瞑想を主体とする厳しい修行が必要なためすべてを捨てて出家せざるをえず、日常の生活を送りながら悟りに至ることは不可能でした。
「苦」とは何か
ここで少し「苦」について書いておきます。釈迦は、苦とは生老病死あらゆるところにあり、特に、物事が自分の思い通りにならないことだと説明しました。「苦」についても「仏教の「悟り」とはどういうことか」という記事に書いてありますので参照してください。
私たちの生活での苦しみとして、病や死といったことに加え、自分の思いとは異なる状態になることが、確かにあります。それは、不安に苛まれ、ストレスまみれになり、怒りの感情を抑えられないことなど様々な状態です。
このような苦しみも私たちの日常生活ではかなり重要なことです。そう考えると、私達にとっては、悟りに至る前に、日常的な苦(意志に反した望まぬ状況)から開放されること、それが重要な目標になるといえそうです。
ちょっと恣意的な感じはしますが、ここでは、わたしたちの日常の悩みから逃れるため、一先ず、悩みが少なく、ストレスが少なく、怒りの気持ちがそこそこ、というように、ネガティブな感情から少しでも自由になることを目標としてはどうでしょうか。
つまり、最初に書いた悟りのランクの2.を狙うことも適切かと思われます。
私達が使える瞑想
よく知られているように、心をコントロールする手法として、禅やその他いろいろな瞑想法があります。瞑想法については、「様々な瞑想法とそれらの特徴」というブログ記事にまとめました。そこでは、禅の瞑想の他に、リラクゼーション型の瞑想とマインドフルネスの瞑想を書きました。それぞれの瞑想の方法、特徴などについてはその記事を見ていただきたいのですが、結論だけ下に書いておきます。
上で書いたいずれの瞑想でも、共通するのは、気持ちを集中することが第一歩です。その先がそれぞれ異なります。
- 禅では、意識を集中しそれを究極まで高めます。
- リラクゼーション型では、意識を集中し心身をリラックスさせます。
- マインドフルネスでは、意識を集中し自分の思考の動きに気づけるようにします。
何故、瞑想には効果があるか
様々な瞑想法があり、それら瞑想法には何故心を安らげる効果があるのかということについても「様々な瞑想法とそれらの特徴」というブログ記事に書いてみました。ここでは、要点だけ書きます。
動物、人が進化する過程で、生き残るためには体、心ともに、環境に瞬時に対応する必要があり、それぞれかなり自律的に動作するようになったのだそうです。そのため、心、意識の面でも、意図しないのに、勝手に、不安を感じたり、ストレスを感じたり、怒り狂ったりするようになったらしいのです。
そのため、意識を集中し、心をある程度コントロールすることができるよになると、随分と心を安静に保つことができるようになります。これが、瞑想により得られる効果といえそうです。
あなたはどこを狙うか
仏教で、悟るということは、無我を会得し、自己が存在しないことを掴むことです。釈迦は、我(自己)というものは存在しないことを言いました。そして、自己が存在しないことを瞑想で掴むことを教えました。
一方、現在では、哲学的、心理学的に、自己、自由意志、自分というのは存在しない、ということが説明されるようになってきています。従って、自己は無い、と悟る道が、普通の人にも道がひらけたと考えてよいようです。
釈迦は、苦とは思い通りにならないこと、とも言っていますが、現在、多くの人々が、ストレスに苛まされ、不安に襲われ、些細なことで怒ったりしています。これらも、思い通りにならない苦に係る問題であることは確かです。現代の我々には、これらが解決できることが、悟りの一面かもしれません。悟りを捻じ曲げている感がなきにしもあらずですが、まあお許しください。私たちにとって、悟りにも等しいものです。
この記事の最初に、悟りのランクを書きました。仏教における瞑想は最終的な悟りを目指すようですが、日常生活を送りながら最終目標にいたるのは難しそうです。しかし、悟りのランク2.であれば、私達にも手の届く範囲にありそうです。