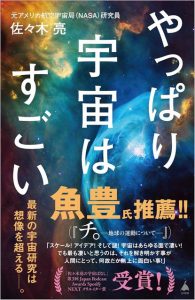「縄文人の死生観」山田康弘(角川ソフィア文庫 2018)
著者は2008年に「生と死の考古学」を出しており、それを文庫化し再出版したのがこの本だということです。
文字記録のない縄文時代の死生観を一体どうやって推測するのか不思議なのですが、著者は、埋葬の方法、状況から、縄文時代の精神文化を研究しています。
墓(埋葬)の研究
前書きによると、墓(埋葬)の研究から、昔の人の墓から社会的地位、精神文化などさまざまな情報が得られる、又、被葬者の生前の情報も得られる。墓のあり方とそこから出土した人骨から、当時の人々の死生観や思想を検討する道が生まれる、ということのようです。
例えば、埋葬の仕方にはいろいろありますが、単独葬であるか合葬かということで家族関係、あるいは系譜が想像できるようです。
又、子供の成長の段階により埋葬の仕方が変わるようで、さらに、妊婦の埋葬は通常の埋葬とは異なるようで、その他の種々のケースでも埋葬の方法が異なることがあり、人のライフステージによる死生観、思想文化が見えてくるようです。
死生観
死生観、つまり、生と死にまつわる縄文時代の思想としては、死後、人は自然に帰り、そして再び人として戻って来る、と考えていたかもしれないそうです。これは、再生観念と呼ばれるものです。もう一つの死生観としては、祖霊崇拝があり、これは、自分がどのような系譜の中にいるのかという出自の歴史的認識だそうです。この2つは絡み合って、弥生時代に続いていくそうです。
最近、「縄文ブーム」と呼ばれるムーブメントがあります。これについては、「縄文で遊ぶ」というのも結構だが、学術的見解は別物であり、そのバランスが必要だと書いています。
以上ざっと書きましたように、墓、埋葬の研究により、縄文時代の精神文化が見えてくるようで、驚きです。
目次
まえがき──墓を研究するということ
プロローグ──発掘調査の現場から
第一章 縄文時代の墓とその分析
第二章 土中から現れた人生──ある女性の一生
第三章 病魔との戦い──縄文時代の医療
第四章 縄文時代の子供たち──死から生を考える
第五章 縄文の思想──原始の死生観
エピローグ