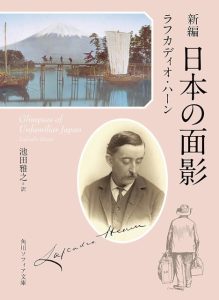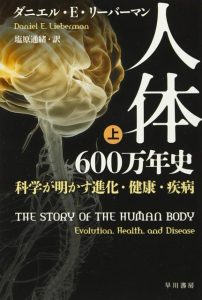「新アジア仏教史11 日本Ⅰ 日本仏教の礎」末木文美士他編(佼成出版社 電子書籍版 2018)
新アジア仏教史はこの11巻目から日本の仏教になります。この巻では、仏教が伝来しそれが広まる状況が書かれています。この巻の目次は下のとおりです。
第1章 仏教の伝来と流通
第2章 奈良仏教の展開
第3章 最澄・空海の改革
第4章 仏教の日本化
第5章 神仏習合の形成
第6章 院政期仏教の展開
特論 女性と仏教
第1章 仏教の伝来と流通
日本の仏教の歴史は、朝鮮からの仏教伝来に始まります。日本書紀あるいは他の資料にその記述があるのですが、例えば日本書紀における仏教伝来とは、国家的伝来であり、民間の伝来ではありません。しかし、考えてみるとすぐ分かることですが、早くから渡来人たちが来ておりその中には仏教を信仰する人もいたことは想像できますので、仏教伝来とは何を指すか、微妙ではあります。
それは、それとして、仏教伝来の時期については、538年説と552年説があります。552年説というのは、日本書紀の仏教伝来の記述なのですが、これは作為的なものと考えられるそうです。もう一つの538年仏教伝来説については、複数の文献があるようで、538年説をとる学者が多いようです。
とはいえ、538年に蘇我稲目に仏教に関する文物が贈られて仏教が開始されたとする話があるとしても、それは、飛鳥寺の古伝であり、歴史的事実かどうかは検証不能です。なお、蘇我馬子は豪族の一人で外交を担当していた、とするよりも、最高権力者だった可能性もあいます。
仏教伝来の時代を語る時、聖徳太子が欠かせませんが、日本書紀では聖徳太子の虚像が作られたため、聖徳太子に関する日本書紀の記述は、殆どが歴史的事実とはみなせないようです。その後、聖徳太子信仰も大いに広まりました。ただし、聖徳太子信仰は日本の文化史、思想史の底流に深く根をおろしており、重要な論点を与えてくれるもののようです。
七世紀前記までは、仏教は蘇我氏とその関係氏族や渡来人の先進文化だったのですが、大化の改新後仏教は各地に急速に広がりました。各地に国立寺院を建立し、仏教制度を整えていきました。国の方針として、仏教と神祇祭祀を使い国家と宗教の結びつきを強めたわけです。そして、民衆にも広がり、多くの人が、修験、山岳修行など、祈祷、呪術の能力を得ようとしました。
旧来の学説では、鎌倉新仏教により民衆への仏教の流布が始まった、とされていたのですが、7世紀末期に民衆へ伝わったのが事実のようです。
第2章 奈良仏教の展開
日本で仏教が広まるにつれて、仏教の内容(教え、戒律など)が重視されるようになったため、いくつかの大きな課題ができました。
一つは、日本がモデルとした中国の仏教の取り込みで、留学僧等によりもたらされた情報は大変貴重でした。
一つは、国家による律令的枠組みの構築です。つまり、国家の仏教はエリート僧が担い、律令制から外れた仏教集団に対しては、放置していては危険な集団(例えば行基の率いる集団)は強く取り締まり、その他の余り害がなさそうな僧尼の活動には無関心で、放任状態だったようです。この奈良時代は、ほとんどの人々が仏教と出会った時代でもあったようです。
一つは、国家の守護、専制権力を支えるシステム、つまり、国家鎮護の呪力装置、天皇一族の災難・穢を祓う役割としての機関の創設で、聖武時代には、国ごとに国分寺と国分尼寺を創建しました。国家鎮護と僧尼の教育をになうとともに、聖武天皇一族の災難・穢を祓う役割が第一でした。
さらに一つ、エリート層を増やすための育成ステム(得度・授戒制度の構築)が整っていなかったため、鑑真の招請は非常に重要な課題でした。
以上のような課題に加え、東アジア仏教の正会員になるためには、もう一つ、教学の整備が重要でした。当時、教学宗派として作られたのが、南都六宗で、三論宗・成実宗・唯識宗・律宗・倶舎宗・華厳宗があります。しかし、当初は低レベルにあったのですが、その後、最澄・空海の登場後以降から日本の教学を確立し中国から自立するよになりました。
第3章 最澄・空海の改革
平安時代、仏教の重大な役割は、飢饉・疫病・天災・怨霊対策でした。国家的なレベル、天皇家、高級貴族の間でも需要があり、それに対して、密教がそれに答えたわけです。天台宗、真言宗は自分等こそが本流であると競い合いますます活性化しました。
そのような中で、空海の密教は真言宗創設の初期から完成度が高かったのですが、天台宗はかなりの出遅れた状態でした。しかし、天台宗では留学僧を次々に送るなど中国からの新しい密教を積極的に導入し優勢に変わりました。最澄の時代は教義が不十分だったので後継者の努力が必要だったことが、その後優位になった理由といえそうです。さらに、よく知られているように、比叡山の仏教は、密教から別れ、様々な宗派がスピンアウトします。
第5章 神仏習合の形成
この章では、古代から中世にかけての神仏習合に焦点をあてています。
「神仏集合」
「神仏習合」とは何か、ということなのですが、神仏習合に対する一般的な理解は、明治の神仏分離政策の結果として定着したのだそうです。つまり、明治政府は、仏教の影響を取り除き昔の本来の姿に戻す、としたことで、神・仏が違うものとして説明する必要がでてきた、というわけです。とはいえ、神仏習合は日本独特の現象ではなく、インド、中国、朝鮮、各地で起きたものです。
「神道」の発見
仏教が伝わって初めて「神道」という概念、言葉が誕生しました。中国も同様に「道教」という言葉が生まれたのだそうです。日本書紀の「神道」は、宮廷における神祀りを指すそうで、よく知られている通り、日本書紀では、仏教と神道の対立を描いているが、歴史的事実は不明なようです。なお、神宮寺の創建は、神仏習合現象の最も早い例で、寺院の守護神として神を祀ることが行われました。
「本地垂迹説」の形成
「本地垂迹説」はよく知られていますが、本地垂迹説がいつ始まったのかははっきりしないようです。9世紀始め頃、延暦寺の僧侶の間から始まったらしく、鎌倉時代には理論的に確立しています。本地垂迹について語る、ということは、神の正体について語るということですが、それが当たり前になった時代、といえます。
また、鎌倉時代から室町時代にかけ、神道論が花開きました。両部神道、山王神道、伊勢神道、吉田神道などです。これらの流れの中で、神道の理論化、体系化がなされました。なお、神官が主導した伊勢神道などに、反本地垂迹説というのがあります(本地垂迹は僧侶側からだされた思想です)。
その後、明治の神仏分離政策により、神社から本地仏が撤去され、権現や大菩薩の神号が廃止されたことは周知のとおりです。
第6章 院政期仏教の展開
この時代の貴族の殆どは自らの来世を仏教に託しました。そして、臨終出家(死の直前の出家)が一般化し、その後、死後も出家を認める風習が生まれました。この死後出家は仏教の教義上ありえないはずのものでしたが、その後仏教儀礼として定着し、現在の死後戒名につながっています。私達は死んだ人を仏さん、というほどその風習が定着しています。
特論 女性と仏教
インドの仏教教団では、男女平等が建前とはいえ、女性に対しての戒律は厳しく地位も低かったようです。中国でも男女格差はありましたが、教学的に優れ高い地位の尼僧もいたそうです。日本でも女性出家者は多かったようですが、それは、女性出家者を巫女、シャーマンと重ね合わせて理解したため、と解釈する説があるようです。
古代から、官尼が官僧と同様法会に出たようですし、実際に尼寺も多かったことは確かそうです。その後9世紀以降、尼寺は減少し、女性は私的な堂や邸宅内の仏教施設を中心に活動したようで、そういうお話し、言い伝えはよく耳にします。とはいえ、「変成男子」、「五障」、「女身垢穢」、女人禁制など、なにかと女性であることの問題があったことも確かなようです。