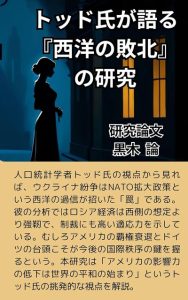「新アジア仏教史06 中国Ⅰ 南北朝 仏教の東伝と受容」沖本克己他編(佼成出版社 電子書籍版 2018)
本シリーズでは、中国の仏教を伝来期、興隆期、持続期と分けていますので、本巻は中国仏教の伝来期に当たります。中国では、インド伝来の仏教思想を「漢訳」(サンスクリット語から漢語に翻訳)するという形で受容しました。そのことが、日本をはじめ東アジア全域への仏教伝播を可能にしたと言えます。一方、中国の目まぐるしく交替する歴代王朝においては、皇帝権力と仏法の摩擦、儒教・道教・仏教の三教にまつわる優劣論争が激化しました。仏教は、中国に昔からあった考え方とぶつかることも多く、又、仏教の平等の精神は皇帝権力とぶつかりやすかったため、何度も廃仏がおきました。
この巻の目次
第1章 中国の仏教
第2章 仏教伝来
第3章 東晋・南北朝の仏教の思想と実践―仏教受容初期の具体像
第4章 三教の衝突と融合
第5章 仏典漢訳史要略
第6章 経録と疑経
第7章 王法と仏法
伝来期
第1章には、中国での仏教受容と受難の歴史が通して書かれています。
仏典が続々と翻訳されましたがその際、中国の人々の伝統的思考に合うように変わっていき、仏教は、儒家や道家とは微妙に異なる新しい「道」の宗教として歩みだした、といえそうです。旧来の思想とは合わず、廃仏もありましたが、隋の文帝のように強力に仏教の復興を進めながら新しい統一国家の完成を目指したケースもありました。
天台宗、三論宗などが生まれましたが、玄奘による新訳経典 中でも、新唯識思想の導入が大きいものでした。さらに、密教の伝播と隆盛もありました。
八世紀末から十世紀末まで、中国における仏典翻訳は完全に停止しましたが、宋代に再開しています。元・明・清の各時代にも若干の訳経は行われましたが、インド仏教の衰退で特に見るべきものはなくなっていたようです。
その後、北魏代に来朝した達磨(六世紀)を祖とする禅仏教が中国仏教の主流となります。
第2章 仏教伝来、では、多数の経典が漢訳され中国で受容されていく過程が書かれています。
仏教は、インドでは暗誦により伝えられたのですが、中国での受容期には仏典の翻訳、つまり経典により伝わりました。その際、中国には、初期仏教の教えと、般若経典などの大乗経典、という2つの系統の教えが同時に伝わりました。三国時代になると、中国に入ってくる仏典を待つだけでなく、玄奘等、西域へ旅立つ人物も出てきました。そして、「法華経」(一乗思想)が入ってきたことにより、仏教経典を統一的に理解する手がかりが得られました。さらに、大乗仏教の中心的な概念である、般若思想の「空」もさまざまに分析されたようです。
仏教が広がる際に、中国で無視できないのが道教です。仏教が入ってきた時、老子、荘子等の中国古典の素養の上に仏教を受容しました。これを格義仏教と呼ぶのだそうです。一方、道教側も、二、三世紀頃には仏教を模倣し教団としての体裁を整えていったようで、更に又、道教経典も作成されました。
又、中国は皇帝が最高権力者であるのに対し、インド仏教は政治を越えた存在であり、これはしばしば論争の種になりました。北魏、北周、唐、後周その他の皇帝の時代に廃仏がありました。