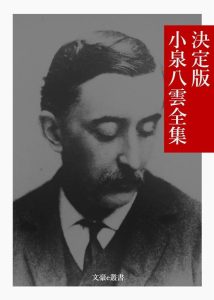「新アジア仏教史07 中国Ⅱ 隋唐 興隆・発展する仏教」 沖本克己他編(佼成出版社 電子書籍版 2018)
本シリーズでは、中国の仏教を伝来期、興隆期、持続期と分けており、本巻は中国仏教の興隆期に当たります。中国仏教は常に国家体制と深くかかわりながら展開したので、教理の変遷だけではなく、国家体制、文化と関わりながら説明した、とのことです。
この巻の目次
第1章 隋唐仏教とは何か
第2章 インド仏教の中国的変容
第3章 教学仏教の様相
第4章 民衆仏教の系譜
第5章 禅宗の生成と発展
第6章 密教の伝播と浸透
第7章 士大夫の仏教受容
興隆期
中国の隋唐時代は、シルクロードを経て伝来したインド仏教が中国的に変容し大きな発展をした時期です。また、末法の世を迎えたとの危機意識があり、求道者の情熱を掻き立てた時代でもあったようです。
その時代、仏教と道教のせめぎ合いがあったのですが、隋王朝は仏教と道教を対等に扱ったようです。しかし、唐王室では、始祖は老子とされたため、道教が強くなり、仏教者の仏教を守る意識はますます強まりました。そして、則天武后と玄宗の時代に仏教が再度巻き戻した、というように状況の変化が厳しかったようです。
なお、隋唐時代に仏教の諸宗派(天台・華厳・密教・禅宗・浄土など)が成立ましたが、当時仏教は学説の違いであり、現在の宗派と称するものとは性格が異なります。
中国の伝統思想と仏教の対立、という視点では、釈迦の教義は父親や君主をないがしろにしますので(出家が勧められるのですから)、中国の伝統的な文化や制度とは合いません。そのため、中国の伝統思想となんらかの折り合いをつけなければ仏教が命脈を保つことは難しかったといえます。
その後、上に書いた諸宗派については、三階教は滅び、天台、華厳、唯識などの各宗派は衰退しました。浄土宗は命脈を保ち、禅宗は中国の士大夫のこころを掴み命脈を保ちました。従来の仏教教団では労働に従事することはできなかったのですが、禅宗では作務や普請が認められ、むしろ、修行者の修行の場、仏法を究明する場となりました。
大乗仏教の空の思想、如来蔵思想、唯識思想などが中国に伝わりましたが、これらの間には根本的に対立する概念もあります。仏性が常住であるか否かは重要で、常住であれば仏性が我(アートマン)になってしまうことになるなど、いろいろと理屈を合わせるために苦労したようです。三論の一つ中論では、「空」「縁起」「二諦」が中心課題で、大乗に合致することから、三論学派が優勢となったようです。
一方、唯識では小乗と大乗を総合した一切乗という立場を主張しました。なお、唯識では、我々が認識しているものは自らの心の現れであり、すべて希有であるとみます。が、仏性に関しては異論が多く、中国で流行した悉有仏性とは相容れないものだったようです。