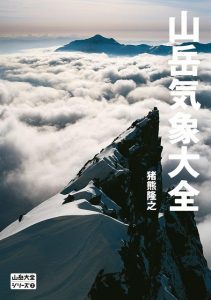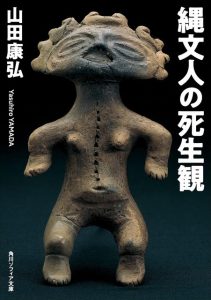「反知性主義―アメリカが生んだ「熱病」の正体―」松本あんり(新潮選書 2015)
新潮社のサイトでは、この本について以下のように紹介されています。
アメリカでは、なぜ反インテリの風潮が強いのか。なぜキリスト教が異様に盛んなのか。なぜビジネスマンが自己啓発に熱心なのか。なぜ政治が極端な道徳主義に走るのか。そのすべての謎を解く鍵は、米国のキリスト教が育んだ「反知性主義」にある。反知性主義の歴史を辿りながら、その恐るべきパワーと意外な効用を描く。
となると、「反知性主義」の意味を知らねばならない。そして、この本から「その恐るべきパワー」と「以外な効用」を読み取らねばならないのですが、それができるでしょうか?
「反知性主義」とは
先ず、「反知性主義」とは何かということですが、歴史のある、多義的な相当難しい言葉のようです。Wikipediaでは、かいつまんで書くと、次のようになるようです。
反知性主義(anti-intellectualism 反主知主義)は、知性に対し意志や感情を優位に置く主張であると『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』は解説している。
政治史家のリチャード・ホフスタッター、および神学者かつ牧師の森本あんりによると反知性主義とは、知的権威やエリート主義に対して懐疑的な立場をとる主義・思想である。
ただし反知性主義という言葉を定義付けたとされるホフスタッターでさえ、それが曖昧な語義の用語であることを認めており、単純に論敵を非難するバズワードとして使用される場合も多い。
著者は、反知性主義とは、知性そのものに対する反感ではなく、知性と権力の固定的な結びつきに対する反感、知的な特権階級が存在することに対する反感である、としていますので、上のWikipediaの説明での森本あんり氏の部分は合っているような合っていないような、、、
アメリカにおけるキリスト教
この本では、反知性主義がどのようにして今の形になっていったのかという歴史が書かれています。この本を読み始めて先ず感じるのは、一言で言うとアメリカの宗教は変わっているな、という印象なのですが、アメリカが何故そうなったのかが読んでいるうちにわかります。例えば大統領選でのあの熱気がどこから生まれて来たかということもよくわかります。
アメリカのキリスト教の歴史の視点からは、アメリカ大陸への初期の移民には知識階級が多く、牧師はほとんど大卒だったようです。しかし、次の時代では伝道に高尚な知識は不要とされ教育を受けていない牧師が増えたようです。つまり、この時代のキリスト教は信仰復興運動(リバイバリズム 回心つまり信仰の再確認)が中心となり、これは、ピューリタニズム(初期の移民した人々の意識)の知性主義への反動でもあったようです。
アメリカにおけるキリスト教の主流的な考えは、「世俗的な成功は神の祝福を得ていることの証」とすることにあり、現在も続いているようです。非常に現世利益的な信仰で、厳格なキリスト教の教えではなさそうです。この本から少し離れますが、キリスト教の神が絶対神であるとすると、教理上、神は人間の一生を最初から知っているし、一人ひとりの思い通りにならない(神は人の望みに左右されない)はずだ、といえそうです。絶対神としてしまうと教理上難しい問題がいろいろと出るようですね。
著者は「アメリカ人にとって、宗教とは困難に打ち勝ってこのようにおける成功をもたらす手段であり、有用な自己啓発の道具である。神を信じて早起きしてまじめに働けばこの世でも成功し、豊かで健康で幸せな人生が送られることが保証されるのである。逆に悪いことをすれば必ず神の審判を受けねばならない」と、現世利益的な信仰の説明をしています。
又、18世紀のアメリカには上流階級がなかったといえますし、何も持たない人間が成功するアメリカンドリームがあったことは確かそうです。が、現在においては、アメリカンドリームが実現する可能性は減りました。しかし、アメリカンドリームというのはアメリカ人にとって依然として夢であるようです。
再度「反知性主義」について
この本のいたるところに「反知性主義」という言葉が出てくるのですが、どういう意味で使っているかは、その都度注意する必要があるようです。とにかく「反知性主義」は難しい言葉です。
エピローグには用語の説明がありますので、下に少し書きます。
<知性>とは
何かを理解したり分析したりしする能力は「知能」であり、さらにそれを自分に適用する能力のあることが「知性」である、ということのようです。
<反知性主義>とは
著者は、次のように書いています。
知性が欠如しているのではなく、知性の“ふりかえり”が欠如しているのである。知性が知らぬ間に越権行為を働いていないか。自分の権威を不当に拡大使用していないか。そのことを敏感にチェックしようとするのが反知性主義である。
ここで「ふりかえり」とは、何かを理解したらそれを自分に適用することと書かれています。更に、著者は「つまり反知性主義は、知性と権力の固定的な結びつきに対する反感である。」と書いているのですが、上の説明とはかなりの違いを感じます。
<反知性主義>のパワー
アメリカにはラディカルな平等主義が存在し、それはエスタブリッシュメントに対する宗教的な異議申し立ての権利であり、信仰復興運動により一般大衆の手に入ったといえます。したがって、反知性主義はどんな学問的権威も吹き飛ばしてしまうような非常に強力な武器といえそうです。
ただし、大衆に立つ側の人が権力を握ったら、あるいは名声を勝ち得たら、往々にして反知性主義で批判される立場になるようです。
目次
プロローグ
第一章 ハーバード大学 反知性主義の前提
第二章 信仰復興運動 反知性主義の原点
第三章 反知性主義を育む平等の理念
第四章 アメリカ的な自然と知性の融合
第五章 反知性主義と大衆リバイバリズム
第六章 反知性主義のもう一つのエンジン
第七章 「ハーバード主義」をぶっとばせ
エピローグ