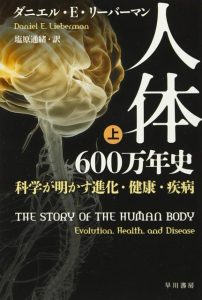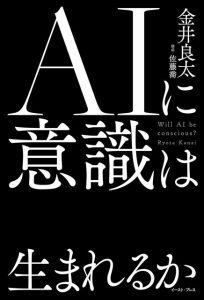「新アジア仏教史12 日本Ⅱ 躍動する中世仏教」末木文美士他編(佼成出版社 電子書籍版 2018)
この巻は、中世仏教史を扱っています。11世紀~16世紀の期間で院政期から戦国期に当たります。以前は、この時代は鎌倉仏教を誕生させ、民衆救済活動に積極的に関わり、社会的にも大きな影響力を持った時代だったとされてきました。そのため、旧版では4冊だったのですが、時代が流れ、現在では鎌倉仏教に対する見直しが進み、新版ではこの期間は1冊になっています。この巻では、新たな中世仏教像がどのようなものであるのか、を記述しています。
各章の内容を以下に要約します。
第1章 顕密仏教の展開
古代律令制の下での寺院は朝廷の支配下にあり、朝廷から供料を支給されていました。しかし、律令制が崩壊するにつれて寺院も経済的な自立を余儀なくされ、諸寺院は自ら荘園を持ち権門すなわち封建領主としての地位を築き上げました。荘園からの収入が寺院活動を支えたわけです。さらなる収入としては、新たに勃興した武士階級、あるいは民衆からの寄付もありました。結局、荘園の集積に成功したのが、東大寺、興福寺等であり、失敗したのが西大寺、大安寺等で勢力縮小していきました。なお、「顕密仏教」とは、南都仏教と平安仏教の総体を意味します。
第2章 新仏教の形成
この章では、鎌倉新仏教を「鎌倉期に祖師により立ち上げられ、室町時代に勢力を確立した仏教教団」とし、各祖師の思想を具体的に分析しています。
戦後の仏教史研究で大きく変わったのは、鎌倉新仏教の位置づけです。思想の研究としては開祖に集中する傾向にあったのですが、より広い視野に立つ歴史学の立場からはその当時にあっては開祖は社会的には影響力の小さいマイナーな存在でした。中世社会における主流は実は旧仏教(南都六宗と天台・真言)でした。
鎌倉新仏教とはどの程度「新」だったのでしょうか。
浄土宗、禅宗、日蓮宗は天台宗の中に含まれており、天台宗とは連続性があり、どこまで「新」といえるか微妙でした。日蓮宗の場合は特にそうだったようです。また、いずれの宗派も勢力を増大させるのは室町時代から戦国時代にかけてであり、祖師たちの思想がそのまま受け継がれたわけでもなく、かなり変容しています。そのため、実体としては、「室町仏教」「戦国仏教」というのが妥当とも言われています。
それにしても、現在の仏教の宗派がどのように生まれたか個人的に気になります。
浄土系
最も新仏教らしいのは法然から始まる専修(せんじゅ)念仏運動です。しかし、専修念仏は異端的とされ、既成仏教からは批判・弾圧されました。その主な理由は、厳しい行をせず、他の神仏の威光を排除した、ということです。ただし、浄土宗側は、極端な排他的態度を抑制し既成仏教との共存の論理を作り、その後どうやら活路を見出しました。浄土宗のヒーローである親鸞は法然の弟子で、本人は独立の一宗をたてるつもりはなかったようで、浄土真宗が大教団になったのは戦国時代の蓮如の活躍によります。
禅宗
中世に輸入された宗派であり、当初、達磨宗が主流でした。一言で言うと、禅宗の主流派はあまりにも権力に近かいものでした。私たちは臨済宗の祖師は栄西、と思っていますが、それは妥当ではないようです。というのは、栄西は密教僧でもあり、栄西は名誉と権威を積極的に求めた人物だったため、一般には人気がなかったようです。そして、臨済宗が宗派として実体化するのは戦国末期のことでした。一方、曹洞宗の祖師とされる道元は人気はあったものの、彼の思想はかなり孤立したもので、中世禅宗の代表とはいえないそうです。道元は、中国に渡り帰国後、禅を説きましたが延暦寺などからの攻撃があり、越前に移り、永平寺を開いた経緯があります。達磨宗の一部が道元門下に入り徐々に勢力を増しました。禅宗全体に関しては、蘭渓道隆、無学祖元らの来日、五山十刹(ござんじっせつ)、五山と林下(官寺でない禅寺)等注目すべきことがありますが、五山派は戦国期の戦乱で衰退し、地方に展開していた林下が禅宗の主流となっていったようです。
日蓮とその教団
日蓮は新しい宗派の独立を宣言しているわけではないようです。日蓮は、天台宗の密教化を批判し、比叡山の戒壇を否定はしている、つまり、当時の天台宗を否定してはいるのですが、決して天台教学そのものを否定してはいませんでした。むしろ、自分が天台宗の正統だ、という意識を持っていたようです。実際、日蓮は天台宗内の異端的な一派くらいにみなされていたといえそうです。
第3章 仏教者の社会活動
日本に仏教が伝わって来て以来、顕著なことは日本には律がないということです。つまり、僧に課せられる規則が重視されていなかった、ということです。その結果として、仏教の共通規範が薄れたため、各宗派は独自の仕方で僧侶を養成することになりました。そして求心力を維持するために各祖師のカリスマ性が必要となりました。つまり、祖師信仰は律の衰退と関連しているというわけです。
仏教者の社会活動というと行基等の活動がよく知られています。全面展開したのは中世の律宗集団でした。ただし、この律宗集団というのは、南都六宗の律宗とは区別すべきもののようです。中世における律宗は、官僧身分を離脱し(遁世僧)戒律と密教を核に在家も含めた教団を形成したた、前の時代とは性格が大きく異なるようです。そのため、中世では、律僧と呼ばれ、近世では真言律宗集団と呼ばれるとのことです。性格が変わったことにより社会的に大きな変化が生まれます。それは、官僧達は葬式など穢に関わることはできなかったが、遁世僧は社会活動に積極的に関与できた、ということです。前の時代には、神仏習合により官の僧達は神社で祭事を行うため、穢れ忌避が義務化されたことによります。中世以降は、律僧を中心に葬送を担うようになった(担えるようになった)というわけです。更には、普段の戒律修行をしているから僧は穢れから守られている、という論理もできあがりました。
第4章 儀礼と神話
ここでは、中世神話と反本地垂迹説のありようが論じられます。
本地垂迹思想は平安末期までに全国に及び、中世神道説(神々に関する教理化)が起きます。伊勢神宮は長い間仏教とは距離をおいていたのですが、奈良時代中期には神宮寺ができ神仏習合が進みました。しかし、道鏡事件の後、その反省から、仏教が忌避されるようなりました。ただし、神は祀られている場所・集団の安寧・繁栄を司るもので、個人の現世や来世には関わらないものであり、仏教の信仰を排斥するものではない、とされました。
その後、天照大神と大日如来との同体説が広まると、僧徒が伊勢神宮を盛んに参拝するようになり、両部神道がひろまります。これは真言密教に近いとはいえますが、違いもあるようです。そして、神々は仏菩薩の垂迹として正当化されていきました。
一方、複数の神道流派が誕生します。外宮神官の度会氏は外宮の地位を高めるため伊勢神道書を生み出していくことになります。反本地垂迹思想が生まれたきっかけは、仏菩薩がそれ自身の姿で衆生に様々の利益を施しているのに、その上で神として顕現するのは何故か、という問題が生じたことにもあるようです。その際、神こそが仏菩薩による救済の日本相応のあり方だ、との解釈が登場し、神祇への信仰を優先すべきとの主張、反本地垂迹思想となりました。吉田神道では、神道を万物の根源とし、本地は神で仏菩薩が垂迹、とするものです。
第5章 室町文化と仏教
室町時代の文化は、それまでの天皇中心の公家文化と武家の文化が融合したものといえます。その中で、明との貿易で人と物の交流が盛んになりました。この交流を支えたのが禅宗の僧侶です。その次代、大陸の文化に加え、和歌・管弦、大和絵他様々な文化が盛んになりました。
仏教としては、禅宗のみが繁栄していたわけではなく、南都六宗、天台宗、真言宗といった顕密諸宗も大きなものだったようです。五山制度のもとで勢力を有した臨済宗と将軍との関係は非常に強いものたありました。
第6章 一揆と仏教
宗教一揆といえば、宗派の教えを守るための運動だったり、いわゆる宗教王国を守るための運動のいずれかであることが普通なのですが、一向一揆は本願寺との一時的な政治的関係、あるいは、山伏他の呪術的民間宗教者に対する警戒により起きました。つまり、宗旨そのものに対する弾圧ではなかったようです。
特論 変貌する日本仏教観
この章は、仏教観と題していますが、古代から戦後、更に現在に至るまでの日本思想史を見ているようでとても刺激的です。
この章では、鎌倉新仏教が「発見」されてきた歴史が説明されます。その後、戦後、家永・井上によって形成された新仏教=中世仏教=民衆仏教論は圧倒的な支持を得ます。ところが、やがて、その根拠が突き崩される疑問が日本史研究者から出てきました。荘園制に対抗する在地領主が自立し武士団が成長するという視点に対する疑問でした。仏教研究の側からは、顕密体制が中世仏教界を支配したことが明らかにされました。いわゆる新仏教は支配的位置にある顕密仏教に対し矛盾をあぶり出し部分的な改革、あるいは異端として位置づけられるという理論、つまり、中世というは顕密体制が依然として中心的な時代であったことが示されます。