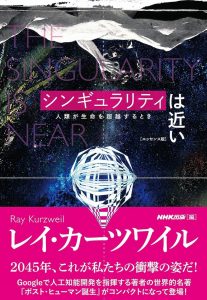「人新生の『資本論』」 斎藤幸平(集英社新書 2020)
この本のタイトルにある「人新生」とは、新生代の中の最も新しい(現在を含む)地質学的な時代のことなのですが、未だ確定したものではないようです。が、人類が地球に大きな影響を与えるようになり、地層にも変化が見えるため、人新生を定めようという動きがあるそうです。ひとしんせい、又は、じんしんせい、と読むようです。
この本では、資本主義は無制限の経済成長を要求し、気候変動をもたらし、必然的に地球環境の破壊をもたらすおそれがあるため、今の資本主義は変えなければならない。従って、経済成長を鈍化させるか停めるかするしかない。その答えとして「脱成長コミュニズム」を提案しています。
資本主義のこれから
現在のグローバル資本主義には問題が山積しており、どうにかせねば、という意見は非常に多いのですが、今後のあり方として以下のように整理できそうです。
1.現状の資本主義を推進する
2.資本主義を見直す(政策、法律を改正する)
3.資本主義に変わる制度を構築する
この本は、3.を主張していることになります。
脱成長コミュニズム
斎藤氏の脱成長コミュニズムとは、インフラはコモン(共有財産)である、生産手段もコモンとして労働と生産を民主化し、経済活動を減速し、富がものをいう社会から脱却すること(←ここ重要です)、労働者の生活の質を高め生活の余裕を生むことにより消費主義的ではない活動への余地が生まれる、というものです。コモンとは、国有でも私有でもない協同組合的なイメージで、自分たちが民主的な管理できる仕組み、ということのようです。
昔(半世紀あまり前)、疎外という言葉を使い、「共産主義下での労働は、資本主義下での労働と質が異なる」という説明を聞きましたが、この脱成長コミュニズムはそれと違いがあるのかどうか、イマイチよく分かりません。
ジジェクは「『進歩』を疑う」(2025)において、斎藤氏の脱成長コミュニズムについて好意的に扱いながらもいろいろ疑問を呈しています。特に、斎藤が思い描く社会は望ましいものか、つまり、快楽を約束しない(過剰な富を否定する)未来に、多数の人が満足するだろうかと言っています。それはもっともな疑問で、斎藤氏もそれは織り込み済みかとは思います。
ということで、グローバル資本主義の進む先は暗い、とは思うものの、脱成長コミュニズムに向かって進んでもよいものかどうか、疑問が残ります。