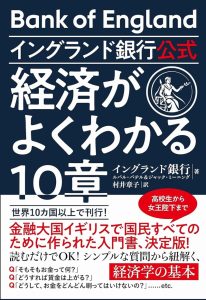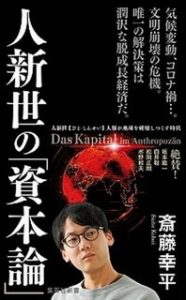「気候変動がわかる気象学」住明正(NTT出版 2008)
本書は、文科系も理科系も含む読者を想定しており数式をできるだけ使わず、天候という最も身近な自然現象の分析法をわかりやく解説したとのことです。
この本の狙い
あとがきには、気象学について、高度情報社会でのツールとしての重要性、更に、個人の楽しみとしての役割を書いています。後者に関しては、以下のように書かれています。
「21世紀は、省エネルギー、省資源の下、個人の楽しみ、豊かさを実現してゆく社会を構築することが大事です。その中では、エネルギーを使わない、資源を浪費しない楽しみ方を見つけることが重要です。外に出て、天気の変化を肌で感じながら、雲の流れを予測し、明日の天気を考えながら一日を過ごすことは、心豊かな日々と思います。ぜひ、挑戦してもらいたいと思います。」
住正明氏の経歴を調べてみると1948年生まれで、私より2歳若いようです。私は後期高齢者になった年に、一念発起して(血迷って)気象予報士試験を受けました。学科試験は最初の受験で合格できたものの、実技試験は三度目の受験でも合格できず、そこで諦めました。今私は、氏のあとがきの言葉に従って生きて参ります。
内容
さて内容ですが、気象というものの本質的なところを掴んでほしい、という意図の伝わる本です。
大気の理解には保存則の重要性。スケールアナリシス。予測・予報のための数値モデリングについて境界値問題、初期値問題、数値モデルなどの基本。地球規模の理論、渦度、各種振動。気候モデルの進歩、大気海洋統合モデルなど気候変動の予測の確実さの向上。その他、現象の下に潜む理論に基づく説明がされています。
期初予報士試験の勉強中は、知識を整理したり、理解を深めることにとても有効でした。特に本質的なところを理解するのにとても役立ったように思います。が、合格できなかった身としてはあまり説得力のあるお話にならないことは承知しています。