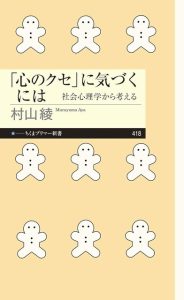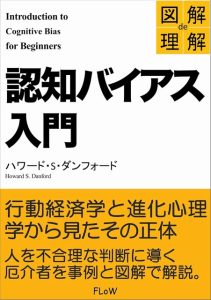「図解 認知バイアス 眠れなくなるほど面白い」高橋昌一郎(日本文芸社 2025)
人には非常に沢山の心のクセ(認知バイアス)があります。このブログでも別記事「『心のクセ』に気づくには」村山綾(ちくまプリマー新書 2024)で、中高生向けに書かれた本を紹介しました。その本では、非常に分かりやすく心のクセを書いています。
それに対し、高橋昌一郎の「図解 認知バイアス」では、もう少し詳しく、様々な認知バイアスについて個々に説明しています。出版社の案内では次のように書かれています。
本書では、数ある「認知バイアス」から、「確証バイアス」「正常性バイアス」「同調性バイアス」「希少性バイアス」をはじめ「ハロー効果」「ダニング=クルーガー効果」「プロスペクト理論」「スリーパー効果」など、読者の関心や興味が強いと考えられるもの、身近で陥りやすい危険の高いもの、知っていると生活にも役立つものを中心に厳選して、図解でわかりやすく伝える。
この本では、脳の詳細な働きなどの難しい説明は最小限にしていろいろな認知バイアスについて個別に見開きで画面を多数用いて説明しています。そのため、認知バイアスの名称とその内容をざっと知りたいときにはとても便利です。私のような記憶力が弱っている高齢者には(詳細については別の資料に当たるとして)この本を手元に置いておいて、おおまかに調べるためいにはとてもよさそうです。
この本の最期に「認知バイアスに陥らないために」という節が設けられています。そこでは、認知バイアスから逃れるために、論理的思考が重要であることが説かれています。
そうなると、論理的思考とは何であるか、ということがとても気になります。著者によると「論理的思考とは、思考の道筋を整理して明らかにすることであって、むしろ発想の幅を広げ、それまで気が付かなかった新たな論点の発見につなげられる思考法です」とあります。しからば、論理的思考を身につけるにはどうしたらよいか、というと「勉強してもらうしかない」とのことです。ここで突き放されたか、とがっくりしていしまいますが、実際にはそうでもなくて、いろいろと説明してくれています。
たとえば、ある論点に関し、賛成、反対のそれぞれ3っつ上げ、それらの論点を整理し、そこから何を重視するかを引き出す、というような訓練をするのがよい、などのアドバイスがあります。その他は本書をお読みください。
なお、この本の章立ては下のようになっています。
1章 個人の意識と認知バイアス
2章 人間関係と認知バイアス
3章 社会生活と認知バイアス
4章 認知バイアスとの付き合い方