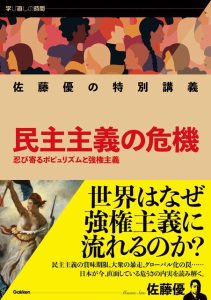「図解de理解 認知バイアス入門」H.S.ダンフォード(FLow ePublication 2022)
心のクセ、認知バイアス
この本では、心のクセ、認知バイアスについて書かれています。私達は何かを考える際、必要な十分な知識に基づき、正しい推論に基づき結果を出しているか、というと必ずしもそうではありません。殆どの場合、人それぞれ独特な判断をしているようです。それが証拠に、わたしたちの言動、行動にはそれぞれクセがあります。同じ場でも人により違った反応をします。従って、十分に考慮し客観的に判断し、話したり行動したりしているとは到底思えません。
心のクセについて非常にわかりやすい本を別記事「『心のクセ』に気づくには」村山綾(ちくまプリマー新書 2024)で紹介しました。
また、いろいろな認知バイアスについてわかりやすい説明のある本を別記事「図解 認知バイアス 眠れなくなるほど面白い」高橋昌一郎(日本文芸社 2025)で紹介しました。
本書の内容
この本では、認知バイアスの生じる仕組みについて、行動心理学、進化心理学を援用し詳細にまで踏み込んでいます。じっくり理解を深めるには有効な本です。本書では、問題を解きながら理解を深める、という形をとっています。実際に問題を解こうとすると大変なことになり、なかなか前に進まなくなります。私はところどころ問題を解くだけ、という怠け者の読み方で読み進めました。
この本にはどのようなことが書かれている、というと、例えば、人は2つの思考態度をとることがじっくり説明されます。それらは、システム1と呼ばれ「直感にゆだねて即座に判断する思考態度」と、システム2と呼ばれ「分析を重ねて論理的に判断する思考態度」です。人は進化の途中で自然の中で危険と隣り合わせで常に瞬間的に判断しなければならない状態にあったためシステム1がとても重要でした。しかし、正しい判断をするには少し時間をかけてシステム2を働かせることも必要でした。人は無意識にこのバランスを取っているようです。この説明は、進化心理学に基づく説明ですが、過去だけでなく今の我々も、周りの人となんとかうまくやっていくためには大勢の人と向き合い瞬時瞬時に判断し適切に振る舞わなければなりませんし、ちょっと時間をかけて十分に考察し間違いの起きないようにしなければなりませんので、この2つのシステムは今の私達にも有効です。
本書では、「確率」、「ヒューリスティック」、「因果関係と相関関係」など興味ある話題が次々に解き明かされます。例えば、私達は確率に弱いことが強調されます。私自身、ベイズ推定に関する問題が出てきたときに、ベイズ推定を確率で議論するよりも、数で考えるほうが分かりやすいことからも実感しています。
認知バイアスは私達を誤らせる困ったものと考えがちですが、実は、進化心理学の視点ではある意味納得させられる深い意味があるようです。
なお、本書は以下のような章立てになっています。
第1章 認知バイアスとは何か
第2章 思考の近道とバイアス
第3章 合理的判断とバイアス
第4章 自己認識とバイアス
第5章 人間関係とバイアス
第6章 損失回避とバイアス
第7章 意思決定とバイアス
第8章 進化とバイアス