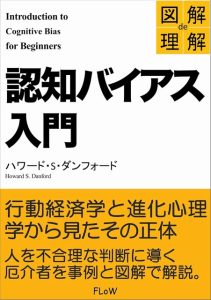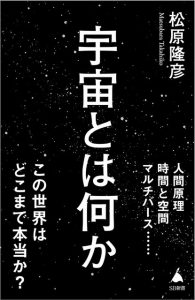「佐藤優の特別講義 民主主義の危機」佐藤優(Gakken 2024)
この本では、現在の日本を含む世界では、新自由主義、グローバリゼーション、金融情報のIT化により、様々な問題が牙をむいています。それに加え、強権的な思潮、ポピュリズムが広まり、そのような状況で、民主主義は生き残ることはできるのか、どうなっていくのかを書いています。
なお、この本は、アメリカでトランプ第二次政権になるかどうかが決まる直前に書かれています。
民主主義とは何か、どう守るか
では、民主主義とはなんでしょう。佐藤優によるとこうです。
民主主義にはさまざまな意見が対立し簡単に定義することができませんが、著者はシンプルに、「民主主義とは、民衆が主体となって行う政治システムである」と考えるようにしていているそうです。そうすると、国民の意見をどうやって代表するのかについて大きな問題が生じます。民主主義と一口でいってもいろいろな政体が変化し続けています。歴史的に見ると、王政国家が僭主政、貴族政、寡頭政を繰り返し、民衆による権力奪取がなり民主政になるのですが、時間が経つと衆愚政(ポピュリズム)、更には独裁政、王政になったりします。結局、政体は変化し、民主主義にも賞味期限がある、ということになるようです。先進国では少し前まで民主主義の時代だと思っていたら、今は、どうやらそれが変わってきていると強く実感させられる時代のようです。
そして、いわゆる民主主義にはいろいろな形態があり、日本や欧米の民主主義がすべてではない、ということも確かなようです。
民主主義は大事、とは思うものの、本書では、「民主主義は正義」と思った瞬間が危ない、とも書いています。上に書いたように民主主義として確かなものが見つかっていないからです。
そして著者は、民主主義の本質を見直さねばならいない。各国はそれぞれ内在的論理を持っていることを前提として考える必要がある、とも言っています。
新自由主義では、独占資本家は決して富の分配を行おうとはしませんので、富の格差は益々進みます。格差の生じることははやむをえないかもしれませんが、新自由主義がもたらす極端な貧困は国家を蝕むおそれがあります。
そこで、筆者は、新自由主義から逃れるには、一人ひとりの身を守るための組織として「中間団体」というものが考えられる、としています。中間団体とは、日本では、中小企業、労働組合、宗教団体、農協などがあります。が問題はうまく機能するかどうかです。
民主主義はグローバリゼーション(資本の国際化)と共存できるか、という問題については、今後グローバリゼーションは変わるだろうという見通しです。トランプは新自由主義者ではなく、保護貿易主義者で、アメリカのこの流れはトランプ後も変わらないだろうと思われ、これは日本にとっても長期的は望ましい方向だとの見立てです。
読後の感想
以上ざっと書きましたように、この本のおかげで、民主主義について整理できました。しかし、それじゃどうする、という部分は私にはもやもや感が残りました。
この本の構成
なお、この本の構成は以下のようになっています。
目次
序章 私たちの民主主義、その限界に気づいているか?
(そもそも、民主主義って何だろう?;民主主義には賞味期限がある、という現実 ほか)
第1章 民主主義を蝕むものとは何か?
(自由と平等をつなぐ「友愛」;民主主義に政党は必要なのか? ほか)
第2章 経済は民主主義を救えるか?
(古典的自由主義と新自由主義は何が違う?;新自由主義が生み出す「格差」の罠 ほか)
第3章 民主主義はグローバリゼーションと共存できるか?
(「生産する国」と「消費する国」;グローバリゼーションって結局どういうこと? ほか)
第4章 ITは民主主義をどう変えるか?
(インターネット投票がもたらす危険とは?;民主主義を分断しかねない「情報過多」 ほか)