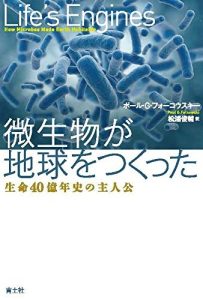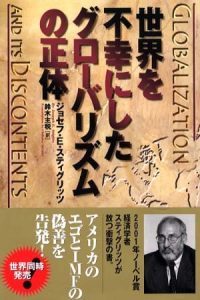「新版 アフォーダンス」佐々木正人(岩波科学ライブラリー 2015)
アフォーダンスの定義
アフォーダンスとは何か、ということを最初に明らかにしておきたいところです。
Copilotの回答は以下のようになっています。がよく分かりませんでした。
知覚心理学者 J=ギブソンの理論。環境の意味や価値は認識主体によって加工されるのでなく,環境からの刺激情報のうちにすでに提供され,固有の形をとっているという思想。
Wikipediaによると、次のようになっています。Copilotよりはかなりましになりました。が、私にはいまいちの感じです。
アフォーダンスとは、環境中の動物(有機体)がその生活する環境を探索することによって獲得することができる意味、あるいは価値である。ここでの価値とは、ある環境において動物に与えられた「行為の機会」「資源利用の可能性」等を指す。
講談社学術文庫には、次のように紹介されています。これだと、具体的な説明になっているので分かったような気もしますが、本当に分かったのかな?
アフォーダンスとは環境が動物に提供するもの。身の周りに潜む「意味」であり行為の「資源」となるものである。地面は立つことをアフォードし、水は泳ぐことをアフォードする。世界に内属する人間は外界からどんな意味を探り出すのか。そして知性とは何なのか。20世紀後半に生態心理学者ギブソンが提唱し衝撃を与えた革命的理論を易しく紹介する。
著書の内容
それでは、佐々木正人著「アフォーダンス」の内容を見ましょう。どうやら、キーワードは、ギブソン、視覚、肌理(きめ)のようです。
従来の視覚論では、目に入った光が網膜で像を結び、その網膜像を脳が解釈して視覚となっている、としています。しかしアフォーダンス理論では、実際には脳の中ではそれ以上のこと、動き、肌理などを理解している、と解釈します。光は空気中や水中で様々に反射し、その結果が眼に入ることになるため、アフォーダンス理論では包囲光を重視するようです。
繰り返しになりますが、一般的な知覚心理学では、刺激を感じ取るとそれを解釈(推論)し意味付けを行うと説明されますが、ギブソンは、推論などしなくても意味や価値は脳が直接知覚できると言います。意味や価値は、環境の中にある面(肌理)やそのレイアウトに表れている、つまり環境のなかにあるため、推論しなくてもダイレクトに知覚できる、世界に意味があると私たちは知っている、と言っているようです。
ここで言う世界の意味は、脳の中で解釈されている、と考えるのが一般的なのですが、アフォーダンス理論では外にある、と考えるようです。
著者は、ギブソンの思想を受け継ぐ学者もいますが、学問の世界では少数派のようです。ただ、実践の場にいる人たちは感覚的にわかるのではないかという気がします、と言っています。また、最近はアフォーダンスという言葉が広まって、スポーツやリハビリテーション、建築デザインなど、さまざまな分野で関心が高まっています、とも言っています。
以上のように、アフォーダンス理論では、脳は環境に意味があることを知っており推論せずにダイレクトに知覚できる、と主張しているようなのですが、脳のなかでは処理が行われていないと断言しているわけでもなさそうで、微妙な感じはします。知覚に関する知見が不足していた時代の理論なのか、それとも今も有効なのか、私には判断がつきません。