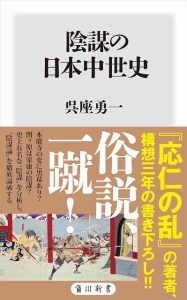「空白の日本史」本郷和人(扶桑社文庫 2024)
この本は、2020年刊の扶桑社新書に加筆し文庫化したものとのことです。日本史におけるいろいろな「空白」つまり「穴」に焦点をあてているそうです。
読んでいくと、ところどころ首をかしげたくなるところもありますが、私の理解が間違えているのか、読み間違いか、よくわかりません。
扱われる話題
この本の紹介のサイトを参照すると、この本で扱われるトピックスは以下のとおりです。
・日本の天皇は、なぜ「キング」ではなく「エンペラー」なのか
・実は3セットある「三種の神器」の矛盾点
・「神仏分離」の誤認が「廃仏毀釈」へと発展
・なぜ、鎌倉時代に貨幣経済が日本で発達したのか
・「崇」「徳」……無念な最期を遂げた天皇に贈られた名前
・日本で軍事史の研究がタブー視されている理由
・「承久の乱の幕府軍は十九万人」が誤りである歴史人口学的な理由
・『吾妻鏡』に記されなかった源頼朝と上総介広常の死
・「色好み」として知られた和泉式部の奔放な恋愛模様
・資料がウソをつくことはあるのか―― 千利休がお金の無心!?
・なぜ光圀は、徳川家でありながら「勤皇思想」に傾いたのか…
感想
上に書かれた話題のうちいくつかについて書きます。
源氏物語などを読んでもわかりますが、平安時代から鎌倉時代にかけての上級貴族の恋愛はかなり自由だったようです。男が女の家を訪ねるという招婿婚が行われた時代でもあり、父親が誰か分からなくなることもあったようです。それが天皇家に関わるレベルでも例外ではなかったらしく、万世一系は確かか、と思ってしまう、と書いてありました。
著者は、陰謀論に理解があるような表現をしています。例えば、第8章「資料がウソをつく ──真相の空白──」には、「・・。ただ、事件の真相については、誰も何も残していないのでわかりません。歴史研究者として語るのであれば、何らかの根拠や筋道を立て、論じるべきだとは思います。でも、歴史上の人物に対していろんな説を出し、楽しむのは、後世に生きる僕らの権利です。どんな陰謀論が 囁かれようとも、そこはまったく問題ありません」という表現があります。前に読んだ、呉座勇一著「陰謀の日本中世史」では、陰謀論を判断する能力を養って欲しい、という気持ちから書いた、という趣旨の表現があり、ほっとけない、ということのようでしたので、この本の著者との違いを感じます。
目次
この本の目次を下に書いておきます。
第1章神話の世界 ――科学的歴史の空白――
第2章「三種の神器」のナゾ ――祈りの空白――
第3章民衆はどこにいるか ――文字史料の空白――
第4章外交を再考する ――国家間交流の空白――
第5章戦いをマジメに科学する ――軍事史の空白――
第6章歴史学の帰納と演繹 ――文献資料の空白――
第7章日本史の恋愛事情 ――女性史の空白――
第8章資料がウソをつく ――真相の空白――
第9章先達への本当の敬意 ――研究史の空白――