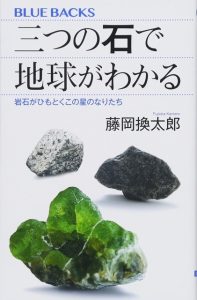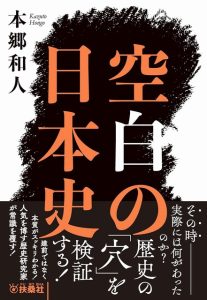「陰謀の日本中世史」呉座勇一(角川新書 2018)
この本のタイトルからは、さまざまな歴史を陰謀論で説明しようとしているようにも見えます。しかし、この本のオビには「俗説一蹴!史上有名な”陰謀”を分析し、”陰謀論”を徹底論破する」とあります。一体どっちなんだ、という感じですが、紛れもなく、陰謀論を批判している本です。
陰謀論に対する姿勢
書籍の案内は売らんがなの刺激的な言葉を並べているのだろうとは思いますが、明快に陰謀論を否定する表現になっています。では、この本の中で。著者は陰謀論についてどのように書いているのでしょうか。まえがきをまとめると下のような感じになるかと思います。
学界には、陰謀の研究を低級だと見下している研究者もいることはいる。陰謀論は謎解きとしては面白いが、学問的にはあまり意味がない。人々が日本史の陰謀に心惹かれているのだとすれば学界の人間も研究対象として取り上げる必要がありそうだ。しかし、自称「歴史研究者」の著作は妄想が大半であり、それを読者が「歴史の真実」を知ったと勘違いされるのも憂慮すべきである。陰謀の真犯人探しは一種の遊びだからそう目くじらを立てることもないと思うが、しかし、私達は日頃多くの陰謀論に囲まれて生きている。陰謀論に引っかからないためにも、何が陰謀で何が陰謀ではないのか見極める論理的思考力が必要だ。そこで、この本では、日本中世史における数々の陰謀を歴史学の手法に則って客観的・実証的に分析していきたい。
という感じで、読者が陰謀論に惑わされないようにするための参考にしてほしい、的な表現です。
感想
歴史マニアでもない私にとっては、この本文を読むと、すべてなるほどなとは思うのですが、実は何が客観的で実証的なのかよく分かってはいません。著者が書いてあることは正しい、しかし、陰謀論を主張する人が間違えていると考えるしかありません。その姿勢は間違えていると思いますが、どうしたら正しいことを見分けることができるのか結局よくわかりません。学界の正論と俗説・陰謀論の違いは?学界外の人が唱えたら俗説?とにかく、私達が十分な知識を持ち正しい推論をする、ということにつきるようです。
なお、この本の著者の説明の中にも主観で判断しているように見えるケースがいくつかあり、それでよいのか悩みます。
又、足利尊氏の優柔不断さを尊氏の性格のせいにすることは批判しています。人それぞれ性格が異なるのは当たり前でそれが歴史にも影響を与える可能性はあると思うのですが、判断する際に人の性格を持ち込むことには否定しているようです。それでよいのか少し疑問が残ります。しかし、それこそ歴史学的にはどうでもよいことなのでしょうね。
目次
もくじは以下のようになっています。
まえがき
第一章 貴族の陰謀に武力が加わり中世が生まれた
第一節 保元の乱
第二節 平治の乱
第二章 陰謀を軸に『平家物語』を読みなおす
第一節 平氏一門と反平氏勢力の抗争
第二節 源義経は陰謀の犠牲者か
第三章 鎌倉幕府の歴史は陰謀の連続だった
第一節 源氏将軍家断絶
第二節 北条得宗家と陰謀
第四章 足利尊氏は陰謀家か
第一節 打倒鎌倉幕府の陰謀
第二節 観応の擾乱
第五章 日野富子は悪女か
第一節 応仁の乱と日野富子
第二節 『応仁記』が生んだ富子悪女説
第六章 本能寺の変に黒幕はいたか
第一節 単独犯行説の紹介
第二節 黒幕説の紹介
第三節 黒幕説は陰謀論
第七章 徳川家康は石田三成を嵌めたのか
第一節 秀次事件
第二節 七将襲撃事件
第三節 関ヶ原への道
終章 陰謀論はなぜ人気があるのか?
第一節 陰謀論の特徴
第二節 人はなぜ陰謀論を信じるのか
あとがき
主要参考文献