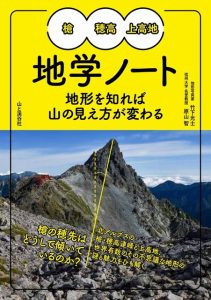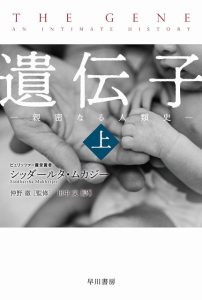「一度読んだら絶対忘れない 哲学の教科書」ネオ高等遊民(SBクリエイティブ 2024)
この著者は、日本初の哲学YouTuberだと自己紹介しています。専門の哲学の研究者ではないようです。
哲学というのは、言葉は難しいし、どうでもいいことをこねくり回しているみたいだし、人の批判ばかりしているし、と凡人にはとても難しい、理解できない学問だという印象があります。そういう難しい哲学の入門として、普通は哲学を時代に沿って説明してくれる哲学史の入門書が重宝されています。
この著者は、哲学史を学ぶ際のポイントをいつくか上げています。その中の一つは、難しい哲学を、正確にわかりやすく理解する方法として「何が重要か、なぜ重要か」がポイントであり、前者は正確に、後者はわかりやすさを意識して書いた、とのことです。また、「哲学は「2つの思想の源流と対立軸」を数珠つなぎにして学べ」といもので、それを意識して説明したとのことです。
この本では、古代ギリシャ、中世、近世・近代、現代と4つに分けて説明しています。上述の対立軸としては、古代では自然哲学と形而上学、中世ではギリシャ哲学とキリスト教、時代ごとにいろいろあるようです。そして、現代では対立軸は崩壊しているそうです。
著者は「始めに」で次のように書いています。「4つの時代区分で15名ずつ、計60名の哲学者を主役に、一度読むだけで哲学の基本が理解できる形式としました」と。私はその言葉に惹かれて全部読んでみました。
4つの時代の中で、中世についてコメントします。中世というのは、神学論争ばっかりでよくわからん、との印象であまり注意もしていなかったため、私にはほとんどなんの知識もない時代です。この本の中世を読んでみましたが、結局何がなぜ重要なのかはほとんど頭に残っていません。なさけないこと、この上ありません。
じゃあ、近世・近代は、現代は、分かったかというと、分かったかなぁ?タイトルの、一度読んだら・・とはいきませんでした。やっぱり、哲学は難しい。