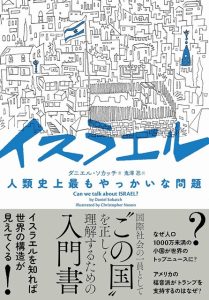「戦後民主主義に僕から一票」内田樹(SB新書 2021)
この本は、過去に書いたいろいろな媒体への寄稿をまとめた本だそうです。紀伊國屋書店のサイトにはこの本について「・・日本の未来を創る上で重要な4大イシュー、民主主義、政治、憲法、教育について、時代を代表する論客が、その争点を示し提言を行う」としてあります。この本の目次は、この記事の最後に記しました。
著者は政治的にはリベラル、護憲派だと思うのですが、さすが哲学者、ということか、話のロジックが普通に耳にするお話とは違っているようです。例えば、護憲派の言説にはリアリティがない、とけなしていますが、もう少し書きますと、護憲派の中心である60代、70代の人たちにとっては守るべきものとして憲法が自然に存在している、つまりリアリティを感じているのだろうが、若い世代には憲法にそのようなリアリティを感じないからだ、と書いています。本当は更にもう少し説明がないと通じないと思うのですが、書くと長くなりますのでこの辺にしておきます(サボりです)。興味のある方はこの本を読んでください。かように?、この著者は、意外性のある話をします。なるほど、そういう見方があるのか、と思わせるところがあります。ある意味フェイントをかけられる感じです。
この本には、下のような一節がありました。
「しかし、せっかく手を拡げて言論活動をしている以上、とりあえずは、どのトピックについても「その分野の専門家が誰も言っていそうもないことを言う」ことを原則にしている。他の人がすでに言っていること、その領域では「常識」として共有されていることを私が繰り返しても意味がないからだ。せっかく発言の機会を頂いた以上は、「まだ誰も仰っていないこと」を言う。そういう方針を採用している」
なるほどな、と思いました。
この本の目次は以下のとおりです。
第1章 民主主義―日本社会の「株式会社化」(民主主義の時代;『民主主義』解説;租税回避と国民国家の解体;対米従属テクノクラートの哀しみ;「語り継ぐこの国のかたち」)
第2章 政治―道徳的「インテグリティ」の欠如(愛国的リバタリアンという怪物;政治指導者の資質とは;独裁者とイエスマン;対米従属のいくつかの病態;「気まずい共存」;リアリズムとは何か)
第3章 憲法―制定過程の主体は誰か?(憲法の話;憲法について;憲法と自衛隊;法治から人治へ)
第4章 教育―貧して鈍して劣化する(教養教育とは何か;大学院の変容・貧乏シフト;大学教育は生き延びられるか?;国語教育について;英語の未来;コロナが学校教育に問いかけたこと)