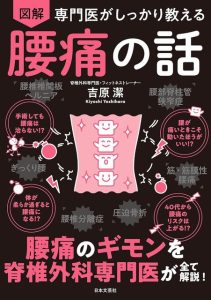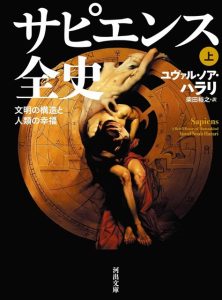「銃・病原菌・鉄」ジャレド・ダイアモンド著(草思社 2000)
こういう大きな学術書の感想を書くのはとてつもなく大変です。おまけにこの本は最初に読んでから随分と時間が経っていたため、記憶が薄くなっており再読の必要がありました。頑張って読み直してみたものの、かなりの部分は流し読みになってしまいました。
さて感想を書こうとすると、Wikipediaにも他のサイトにも、本書の概要、批評などが書かれており、これらを見るとなおのこと感想は書きづらくなりました。でも、気を取り直して書きましょう。
大事な視点
現在、人類は世界中に広がっており、非常に多様な文化・文明を持っています。しかし、10万年前にアフリカを出てしばらくの間は、地域間で道具の制作、利用などにそれほど大きな違いはなかったようです。何故、今のような多様性をもつようになったのか、というのが本書で明らかにしたい点のようです。
例えば、メソポタミアで文明が発展したのは、栽培可能な植物、家畜化可能な動物があったこと、狩猟採集に適さない土地であったこと等が文明発達の理由であり、人々の能力や文化的価値観の差ではない、としています。最初に読んだとき、なるほどなぁと感じました。この、なるほどなぁ、を随所で感じました。
各章の要点
一応目を通したふりをするために、章ごとにどのようなことが書かれているか以下に示します。
第1章 1万3000年前のスタートライン
スタートラインでは、世界各地に広まった人類の生活に大きな違いはかった。
第2章 平和の民と戦う民の分かれ道
環境により社会に違いが生じ、征服者と非征服者に別れた
第3章 スペイン人とインカ帝国の激突
スペインがインカ帝国に対し優位に立てたのは、鉄製の銃等の武器を持っていたこと、天然痘などの病原菌でインカを滅ぼすことができたこと、が大きい。
第4章食料生産と征服戦争
動物の家畜化、植物の栽培化で食料に余裕ができ人口が増し、官僚他の組織が生じた。
第5章 持てるものと持たざるものの歴史
食料生産が独自にできるようになったのは、世界で数か所で、最古はメソポタミア。
第6章 農耕を始めた人と始めなかった人
野生の穀類を栽培する技術を得たと同時に栽培のメリットが増した。
第7章 毒のないアーモンドの作り方
突然変異によって、栽培種の生産性を上げることができた。
第8章 リンゴのせいか、インディアンのせいか
メソポタミアは栽培種に移行しやすい野生種が多く、家畜化可能な哺乳類の種類も多かったため、他の地域より有利だった。
第9章 なぜシマウマは家畜にならなかったのか
家畜化しやすかった動物は多くがユーラシア大陸にいた。
第10章 大陸が広がる方向と住民の運命
栽培化や家畜化に適した動植物の伝播は南北方向よりも東西方向の方が速かった、つまりユーラシア大陸のほうが広がりやすかった。
第11章 家畜がくれた死の贈り物
ユーラシア大陸は病原菌を媒介する集団性の家畜が多かったため、感染症が広がりやすかった。
第12章 文字を作った人と借りた人
文字を作り出したシュメール、メキシコ南部、中国、エジプトやその文字を早期に取り入れた地域は社会制度が整うのが早かった。
第13章 発明は必要の母である
技術は、人口が多く食料の生産性の高い地域で発達しやすく、東西方向に伝搬しやすい。
第14章 平等な社会から集権的な社会へ
社会の規模が膨らみ始めると意思決定の早い社会が優位になり、部族社会の併合が繰り返され国家になっていく。
第15章 オーストラリアとニューギニアのミステリー
オーストラリアやニューギニアでは主食の根菜が低カロリーで、人口の増加が難しかった。
第16章 中国はいかにして中国になったのか
各地方で固有の文化が進展し集権的国家が生まれた。
第17章 太平洋に広がっていった人々
フィリピンからインドネシア・ニューギニアにかけて住む人々は、遺伝子、言語とも違いは少ない。
第18章 旧世界と新世界の遭遇
ヨーロッパの人が南北アメリカ大陸を征服したが、その逆ではなかった。
第19章 アフリカはいかにして黒人の世界になったか
文化や動植物の南北方向の移動は時間が掛かった。
こいうのも何ですが(無責任ですが)、とにかく本書の一読をお薦めします。