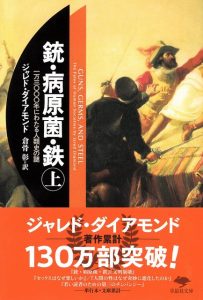「サピエンス全史」ユヴァル.N.ハラリ(河出文庫 2023)
ジャレド・ダイアモンドの「銃・病原菌・鉄」について感想を書きましたので、ハラリの「サピエンス全史」にも触れないのはなんだかなぁと思い、この記事を書きました。ただし、この2つの書籍の出版年代は20年程離れているます。ダイアモンドは地理的・環境的な面から人類の歴史を記述し、ハラリは人の認知能力・文化的な面を重視し人類史を記述したといえそうです。
これだけの大きな学術書だと、読むのもなかなか大変です。第1部の認知革命の辺りは結構集中して読んだのですが、徐々に集中力が途切れ、途中からはいい加減な読み方になりました(他の方々はそんなことはないと思いますが)。
人類の歴史
著者は、「認知革命」、「農業革命」、「科学革命」の3つの革命を軸に歴史を捉えています。本書では、現在までの人類の歴史を4つに分けて説明しており、下は、Wikipediaを参考にした目次です。
第1部(4章): 認知革命(紀元前7万年頃、サピエンスに想像力が備わり現代的行動の始まり)
第2部(4章):(第一次)農業革命(紀元前1万年頃、農業の発展)
第3部(5章):人類の統一(紀元前34年頃、グローバル化に向けて人類の政治組織が徐々に強化)
第4部(7章):科学革命(紀元後1543年頃、客観的科学の出現)
人類は虚構を信じるという(想像力溢れる)能力に富むため、宗教、国家、貨幣などの制度を生み出しました。しかし、著者は、新たな制度、新たな段階で、人は幸せになっているかを常に問いチェックしています。例えば、狩猟採集の時代の人々が生きるために必要な労働時間は、農耕の始まりで改善されたか?悪化したのではないか?という具合です。又、現代の人々が過去の時代と比べて幸福になったか?著しく幸福になったとはいえない、といった具合です。
3つの革命
まず認知革命については、サピエンスは大勢が協力し合う能力があるために繁栄できたとしています。さらに、サピエンスは、宗教、国家、貨幣など、虚構の権威を信じることができたから広域にわたる国家を作り上げることができた、としています。
農業革命については、動物の家畜化や植物の栽培化が可能となり生産に余剰はできたものの、サピエンスの生活から変化を奪い、生活の質を低下させた、としています。
科学革命については、ヨーロッパにおける大きな発展があったが、現代の人々が幸せになっているかどうかは分からない、としています。又、科学術の発展はサピエンスとしての種を終わらせるかもしれない、としています。