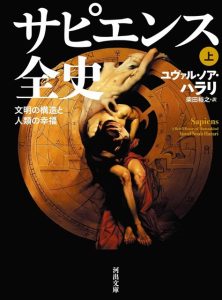「『代謝』がわかれば身体がわかる」大平万里(光文社新書 2017)
私達(他の生命も)は、外から取り込んだ酸素や栄養素を化学反応によって消化・吸収してエネルギを生成し活動しています。この化学反応により物質の変化を代謝といいます。しかし、代謝を説明することはかなり難しいようです。この著者も以下のように書いています。
はっきりいって、生物や医療を専門としない方々に、代謝について語るというのは、かなり無謀な試みであるが、様々な(奇妙な)比喩を活用しながら、なるべく略することなく、最低限押さえておきたい代謝の仕組みを本書では解説した。
著者が言うように、この本では様々な比喩を使って、私達でもイメージが作れるように工夫しています。例えば、あるクラスでのグループ分けの場面を使い触媒の説明をしています。反応の際に触媒とは反応速度を早める物質です。グループ分けの場合、生徒だけではなかなか決まらないが先生が間に入るとさっと決まる、といった具合です。
化学反応における、この担任のような存在を「 触媒」という。「触媒」をきちんと説明すれば、「化学反応において、それ自身は変化せず、化学反応の進み方を変える物質」ということなのだが、まずは生徒どうしの間を取り持つ担任のようなイメージを「触媒」に対して持っていただければよい。
次に、酵素のお話も比喩を使って説明されます。酵素とは、触媒としての機能を持ったタンパク質(例外はあるらしいが)です。
更に酵素のお話が進みますが、さまざまな反応を進めるにはエネルギーが必要です。生物はATPを用いてエネルギーのやり取りを行うそうです。エネルギーを持った物質ATPを合成するための仕組みに、解糖系、クエン酸回路、電子伝達系、・・・がある、という説明が続きます。そして、解糖系、つまりグルコース(ブドウ糖)の代謝の説明になるのですが、とてもややこしくて、この記事に簡単に書けるようなものではありません。それよりも、このプロセスを理解できる人は神様ではなかろうか、と思うくらいすごいことになっています。で、私は、ここでギブアップ。
後日、気持ちを整理して改めて読み直しをしてみましたが、解糖系だけでは必要なエネルギーを賄えない、って書いてあり、えー!!っとなって、やっぱり撃沈しました。
いつか若返って頭が少し良くなったら再挑戦できるかなと思い、本の最後の方をみると参考図書が書いてありました。なんと、そのうちの何冊かは電話帳の厚みがあるそうです。多少頭がよくなったくらいではてもとても無理そうです。