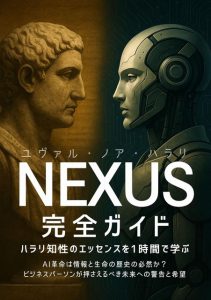「宇宙からいかにヒトは生まれたか―偶然と必然の138億年史―」 更科功著 (新潮選書 2016)
タイトルからは、この本が生命の宇宙起源説を述べている本のように見えるかもしれませんが、この本は地球上の生命の歴史であり、宇宙が生まれ地球が誕生して生物が生まれ人類に至るまでの歴史を書いています。
本書の特徴は、「はじめに」の記述によると、基本的なキーワードはじっくり説明、人間中心主義は排除、等とあります。私が印象的だったのは、順序だった説明で読者にも考えさせながら展開する話の進め方です。とてもわかり易くて、表現がとても柔らい本です。
この本に関し、いくつか。
<人間原理>
この宇宙は人間に都合よく調整されている、あるいは、人間が生まれるくるように調整されている、と考えるのが人間原理ですが、著者は、人間原理をやんわりと否定しています。否定の仕方が心地よく感じます。
<天文に関する疑問点>
説明に引っかかるところもありました。例えば、現在一般的に宇宙は膨張していると認められていますが、そこで何が膨張しているのか、という話題です。宇宙の中のすべてが膨張しているかというと、銀河と銀河の間は膨張しているが、我々は膨張していない。我々が膨張していないから膨張していることがわかるのだ。と説明していますが、どうも腑に落ちません。宇宙の大きさを測るには、身の回りにある定規ではなく、多分光がメジャーになっていると思われますので、我々が膨張していても測定できるはずではないでしょうか。我々が(太陽系等が)膨張しないのは他に理由があるのだと思われます。例えば電磁力と重力とかなんとかが。あるいは実は我々の周辺も膨張しているかも。
月の公転周期は過去からどんどん大幅に伸びた(月が地球から遠くなった)そうですが、その理由を潮汐力を使わずに説明しているようにみえます。少なくとも潮汐力を脇役においているように見えますが、正しいのでしょうか?
<生命の発生>
生命がどのように発生したか、まだ明確にはなっていないようですが、セントラルドグマからはDNAが起点となるDNAワールド仮説、他に、RNAワールド仮説、タンパク質ワールド仮説とあるようです。著者はタンパク質ワールド仮説に傾いているように見えますが、その説明がわかりやすく書かれています。
生命のふるさとはどこか?すべての生物の最終共通祖先 LUCAがどのように推定されるか?真核細胞はどのようにできたか?など新たな疑問が次々と展開されますが、どの話題も、推理小説風に話がすすみ、非常に面白く読めます。
読み終わった感想としては、とにかくわかりやすく読みやすい本です。あまり断定的なことは書いておらず、読者に推理させようとしており、わからないことはわからないと素直に書いてあります。子ども(私の場合は孫)にも安心して読ませられる本です。
目次
以下に目次を書いておきます。
第1部 宇宙の誕生(138億年前~)
第1章 たくさんの宇宙/第2章 ビッグバン/第3章 太陽系の誕生
第2部 地球の形成(45・5億年前~)
第4章 地球と月の誕生/第5章 地殻の形成/第6章 大気と海の形成
第3部 細菌の世界(40億年前~)
第7章 生命の誕生前夜/第8章 生命の起源/第9章 初期の生命/第10章 光合成
第4部 複雑な生物の誕生(19億年前~)
第11章 真核生物の誕生/第12章 多細胞生物の出現/第13章 スノーボールアース
第5部 生物に満ちた惑星(5・4億年前~)
第14章 カンブリア爆発/第15章 生物の陸上進出/第16章 大森林の時代/
第17章 恐竜の繁栄/ 第18章 巨大隕石の衝突/第19章 哺乳類の繁栄/
第20章 人類の進化
最終章 地球と生命の将来