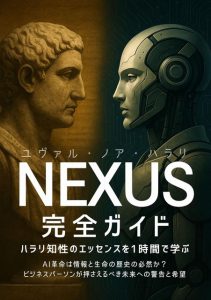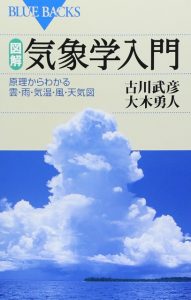「新説 恐竜学」平山廉(カンゼン 2019)
恐竜に関する知識はどんどんと更新されているようです。この本には最新の恐竜学が示されているということです。
最初にこの本の目次を、紀伊國屋書店のサイトから引用して掲載します。
目次
【特別ページ】
2018年6月に岩手県久慈市小久慈で発見されたディラノサウルスの歯化石。それは国内の白亜紀後期では、初の確実なティラノサウルス類であると考えられるものだった。発見現場のレポートと共に、今回の発見の意義を平山廉教授が徹底考察する。
【第1章 恐竜の基礎知識】
最新の恐竜についての基礎知識を解説。ここ10年ほどの間に日本国内でも新種の恐竜が見つかり、さまざまな研究が進んでいる。恐竜とはいったい何なのか、どんな大きさだったのか、絶滅の理由などについて解説。
【第2章 昔と違う! 最新恐竜学】
最新研究によって判明した事実をベースに目からウロコの情報を解説。かつての恐竜図鑑と大きく異なるさまざまな情報を解説。
【第3章 人気者たちの意外な姿】
ティラノサウルス、トリケラトプス、ステゴサウルス、スピノサウルスなど、人気の恐竜の最新情報を掲載。
なるほど、へぇー
以下に、私が、へぇーそうなのかと思ったお話を書きます。
<恐竜とはなにか>
「恐竜とは鳥盤類か竜盤類のいずれかのグループに属する生き物」ということのようです。恐竜以外のほとんどの爬虫類は身体の横方向に向かって脚がのびており、恐竜は下に向かってのびています。意外だったのは、恐竜という種が生まれたばかりの頃、すべての恐竜は後ろ足だけで立って歩く動物だったそうです。四足歩行する恐竜もいますが、その後の進化によって四足歩行になったようです。
<恐竜という種>
卵は硬い殻になっていた。恐竜は、少なくとも体の一部が羽毛で覆われていた可能性が高い。細く長い首を持ったフタバスズキリュウなどの首長竜は恐竜ではない。首長竜はトカゲやヘビに近く、恐竜はカメやワニに近いらしい。といわれてもピンとこないが。など、意外なお話がいろいろと書かれています。
<大型化した恐竜>
竜盤類には、そこから鳥類が別れた獣脚類、非常に大型な恐竜の生まれた竜脚類があります。竜脚類がなぜ大きくなったのか、捕食者から身を守るため、効率よく行きていくため、などが考えられています。また、性選択があったかもしれません。恐竜というと大型恐竜を思い起こしますが、大きな体を支えたのは吊橋構造だそうです。
<恐竜絶滅に関して>
中生代白亜紀末期の恐竜絶滅は隕石によるもの、といわれていますが、隕石落下したその後、生き残った恐竜も多いのだそうです。白亜紀末期に恐竜が絶滅したのは北米が中心で、その他の大陸ではいつ絶滅したかあまりはっきりしないことが多く、恐竜絶滅には隕石以外の他の理由があるかもしれない、と考えられているようです。実際、恐竜は絶滅の数千年前からゆっくり種を減らしていた事実もあるらしく、白亜紀末期には海水水温が低下していたようでもあります。著者が考えているのは、当時種類を増やしていた哺乳類との生存競争が大きく影響しているのではないか、とのことです。小さな哺乳類の数が増え生態系に不安定さが増し恐竜が滅んだ、との考えのようです。
<恐竜の理解>
この本を読んだ後、恐竜理解が変わりました。上に書いたさまざまなお話の他にも多くの事実が分かってきたそうです。
恐竜の立ち姿は、昔とはちがうようです。背骨は地面に対して水平に近く、尻尾は持ち上げているのが最近の恐竜の姿です。竜脚類も最近は頭を下げて低くしています。恐竜には羽毛があった。羽毛には派手な色があったかもしれない。現代の鳥類は、獣脚類から派生した。つまり、恐竜の子孫。ティラノサウルスの目は両眼視できなかったはず。など、楽しいお話は尽きることがありません。