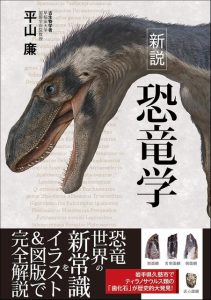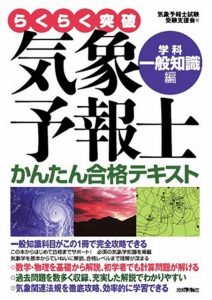「図解 気象学入門」古川 武彦、 大木 勇人(ブルーバックス 2011)
気象のしくみを知りたい初心者には先ずこの本を推薦します。私が読んだのは初版ですが、今は第2版が出ています。
講談社の書籍案内には、「気象と天気のしくみを原理から詳しく丁寧に解説した「わかる」入門書。やさしい語り口ながらも気象学用語の多くを網羅。気象予報士を目指すスタートにも最適」とあります。
気象予報士試験の勉強
実は私も、2021年頃に気象予報士試験に挑戦する際、この本も参考にしました。なお、私は試験に合格てきていないことを先ず告白します。従って、この記事に説得力がないことはもとより承知です?
気象予報士試験を受けてみようと決心した時、受験用のテキストとして、先ずは、技術評論社の「気象予報士かんたん合格テキスト一般知識編」を購入し、勉強を始めました(この辺りのことは、このブログの別記事に書きました)。このテキストは完全に受験用のテキストで、試験問題を解くときに必要なことは書いてあるようです。しかし、気象に関してある程度以上の知識がない人が、最初にこのテキストを読んでも、知識は増えても基本的なところを理解できないまま先に進むことになるかもしれません。記憶力が十分に強ければ、テキストをそのまま記憶して試験問題を解くことはでき、合格レベルに達すると思われます。しかし、私のような高齢者はあまり記憶に頼ることができないため、どうしても現象の裏にある理屈を理解する必要があります。つまり、何故そうなるかという理屈の助けを得て試験問題を解く、ということになります。そのため、どうしても、先ずは気象のしくみをある程度理解しなければなりません。私は、この「図解 気象学入門」を併用して勉強を進めました。この本は、かなり以前買った本で、受験の前に既に読んでいたのですが、受験の際は問題意識の異なる読み方をしましたので大変役に立ちました(最終的には無駄だったのですが)。
目次
目次はつぎのとおりです。
1章 雲のしくみ
2章 雨と雪のしくみ
3章 気温のしくみ
4章 風のしくみ
5章 低気圧・高気圧と前線のしくみ
6章 台風のしくみ
7章 天気予報のしくみ
分かりやすい記述
この本では、雲が何故浮くか、から始まり、雲や雨のでき方、気圧というものの考え方、高気圧低気圧が何故できるか、など気象に関する基本的な事柄が分かるようになります。この本で基礎力がついていると、小倉義満氏の名著「一般気象学」も怖くないと思います。