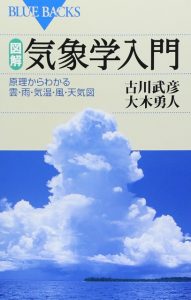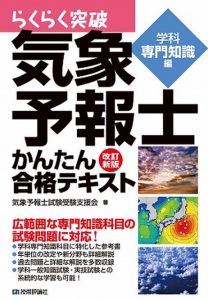「気象予報士かんたん合格テキスト 〈学科一般知識編〉 (らくらく突破) 第2版」気象予報士試験受験支援会(技術評論社 2011)
私は、後期高齢者になる年齢で思い切って気象予報士試験を受ける決心をし、2021年にこのテキスト(400頁に近い分厚い本)を購入しました。これは、一般知識の分野のテキストで、その時既に第2版 第13刷でロングセラーでした。内容は古いのですが、一般知識の分野ですので未だ使える感じでした。ただし、現在は品切れです。
気象予報士試験
気象予報士試験は、学科と実技に別れており、学科は更に一般知識と専門知識に別れています。このテキストは一般知識編で気象の基礎的な分野をカバーしています。なお私は気象予報士試験の実技試験には合格できませんでした。が学科試験(一般知識と専門知識)は合格していますので、この記事の学科試験の部分はある程度信用していただいてもよいかもしれません。
さて、受験を思い立ったとき、受験用のテキストとしてはどの本を使えばよいのか迷いましたが、このテキストを購入し勉強をはじめました。少し読み始めて気がついたのですが、このテキストは完全に受験用のテキストです。受験に必要なことは書いてあるのですが、気象に関してある程度の知識がないと、つまり全体が把握できていないと、個々の項目を勉強してもちょっと効率が悪そうでした。そのため、他の本を用いて基礎知識をインプットしておいてから、再度このテキストに取り掛かり、練習問題も含め、2度ほど読みました。このあたりの経緯はこのブログの別記事に書きました。
他の人も書いているのですが、気象予報士試験の勉強方法としては、過去問を解くのが非常に有効なようです。過去問を解きながら必要に応じてテキストを見るのがよさそうですので、その後は、過去問中心の勉強に移りました。
このテキストの目次
目次はつぎのようになっています。
第1章 地球型惑星と大気の構造
1-1 地球型惑星の大気構成
1-2 大気の鉛直構造
1-3 地球大気における循環
第2章 水の状態変化と水分量の表現
2-1 水の状態変化と潜熱
2-2 大気中の水分量の表現方法
第3章 雲の種類と降水過程
3-1 十種雲形
3-2 降水過程
3-3 雲粒と雨粒の最終落下速度
第4章 大気における放射
4-1 電磁波と波長
4-2 散乱
4-3 地球大気における反射
4-4 放射に関する法則
4-5 太陽放射と地球放射
第5章 熱力学の基礎
5-1 原子と分子
5-2 ボイルの法則、シャルルの法則
5-3 理想気体の状態方程式
第6章 熱力学の応用
6-1 気体の状態方程式
6-2 熱力学の第一法則
6-3 静力学平衡
6-4 大気の気温減率と安定度
6-5 温位
6-6 相当温位
6-7 エマグラムに関する知識
第7章 大気の力学と運動
7-1 大気に働くさまざまな力
7-2 地衡風
7-3 傾度風
7-4 旋衡風
7-5 地上風
7-6 温度風
7-7 大気境界層
7-8 発散と収束
7-9 渦度
第8章 大気の大規模な運動
8-1 大気の子午面循環
8-2 前線帯とジェット気流
8-3 南北熱輸送
8-4 大規模な気象現象
8-5 偏西風波動と温帯低気圧
第9章 メソスケールの現象
9-1 ベナール型対流
9-2 雷雨
9-3 台風
9-4 海陸風と山谷風
9-5 フェーン現象
9-6 メソ対流系
第10章 中層大気の運動
10-1 中層大気の特徴
10-2 その他大気の諸現象
第11章 異常気象と気候変動
11-1 異常気象と気候変動の外的要因
11-2 異常気象と気候変動の内的要因
第12章 気象法規の知識
12-1 気象業務法
12-2 災害対策基本法、消防法、水防法
12-3 気象関連法令集
付録 数学・物理の基礎
付録-1 数学の基礎
付録-2 物理の基礎
なお、各章ごとに練習問題と解答解説が付いています。