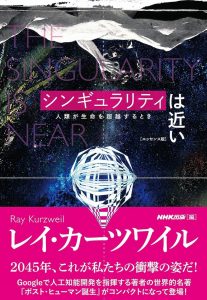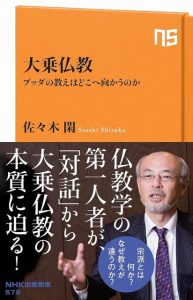「『時間』はなぜ存在するのか」 吉田伸夫 (SB新書 2024)
タイトルは「時間」はなぜ存在するか、ですが、内容は、時間に関する様々な疑問・不思議に答える、という書き方になっています。具体的には、時間が流れるように感じられる理由、宇宙の始まり、宇宙の終わり等の説明がなされ、その間に、SFなどの楽しいお話が挟まれています。以下に、いくつかの話題を書きます。
宇宙の始まり
昔私が聞いていたお話では、宇宙はビッグバンという爆発から始まったとされましたが、その後研究が進み、現在は、宇宙が生まれ先ずインフレーションがありその後ビッグバンが起きた、とされているようです。インフレーションとは、生まれた宇宙がそれ自体に備わっているエネルギー(暗黒エネルギー)の効果で膨張を続けることだそうです。そして、インフレーションの段階では宇宙には物質はないのでエネルギーの偏りがなくエントロピーは最小だったのだそうです。ところが、ある段階で物質や力の場が生まれ物質に満ち溢れた世界になったのがビッグバンなのだそうです。この説明はインフレーション理論と呼ばれているものの一つで、たくさんのバリエーションがあり決定打はない、とのことです。私もいろいろな解説書でいろいろな説明を聞いてきましたが、吉田氏の説明はなるほどと好意的に感じました。
エントロピー
エントロピーに関する説明については、わかりやすさを狙いすぎたのか、説明の仕方に多々疑問を感じました。
本書には、サイコロを使った解説がありましたが、誤解されそうな説明です。たくさんのサイコロを箱にいれて箱を振動させると目がどんどん変わっていきます。そこで、最初に1111(ここではサイコロを4個4とします)だったのが振動を与えると例えば4352とかいろいろなランダムな値になります。最初は規則性があったのにランダムになるのでエントロピーが増大した、という説明になっています。しかし、こここでは1111が特別だとされていますが、4532も特別な組み合わせであることに違いありません。1111が発生する確率も4532が発生する確率も同じです(順序・位置は無視しています)。説明にもう少し工夫が必要そうです。
振り子を使った説明も引っかかりました。振り子の錘(おもり)が時間とともに揺れが小さくなることを、錘と周囲の空気の相対速度の問題としてエントロピーを用いて説明しているのですが、どうもピンと来ませんでした。
エントロピーに関しては、以前このブログの別記事「どうして時間は『流れる』のか」(二間瀬敏文著)の方が確かそうな表現になっていると感じました。
観測問題
観測問題というのは、Wikipediaによると「量子力学においてどのように波動関数の収縮が起きるのか(または起きないか)という問題である。あるいは観測(観察)過程を量子力学の演繹体系のなかに組み入れるという問題と言い換えることもできる。収縮を直接観測することができないため、様々な量子力学の解釈が生まれ、それぞれの解釈が答えねばならない重要な問題を提起している」だそうです。また、解釈については、依然としていろいろとバリエーションがあるようです。
吉田氏は、観測行為で重要なのは、人間による観測行為ではなく、測定装置のような巨視的な物質の統計的な振る舞いであることが判明した、と言う点を強調しているように感じます。私としても、以前から、なぜ人間による観測行為が問題にされてきたのか、が実は肌感覚として分かりませんでしたので、それはそれで納得です。そして、吉田氏は、観測問題の話題として、多世界解釈に移っています。
宇宙の最期
現在、宇宙は拡大中であることが観測から明らかになっています。このまま広がり続けるとどうなるのか、という問題です。吉田氏の説明では、宇宙がどんどん膨張し、そのうちブラックホールだけになり、最期にはブラックホールが蒸発する、となっています。
実は、上でも触れたこのブログの別記事「どうして時間は『流れる』のか」(二間瀬敏文著)では、宇宙の最期はブラックホールだけになるのか、ブラックホールも消えてしまうのか、読んでみても分からない、と書いたのですが、吉田氏はブラックホールもなるくなる、と書いてあります。気分的にはすっきりしました。