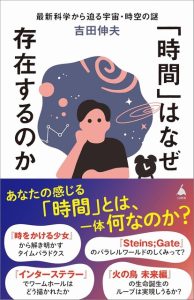「大乗仏教 仏陀の教えはどこへむかうのか」佐々木閑(NHK出版新書 2019)
この本は、過去に読んだ仏教関係の解説書の中で最もインパクトを受けた本の一つです。この本のおかげで、私の仏教への理解は一段上がったような感じがしました。この本では、数ある大乗仏教の経典(お教)からいくつかを選び、その特徴、違いを非常に分かりやすく書いてあります。なお、この本では宗派の違いを説明するのではなく、経典そのものを説明しています。私は、佐々木氏の記述に感激し、他のブログに「寺社訪問 虎の巻 大乗仏教の誕生と大乗経典の変遷」という記事を書きました。
別ブログの私の記事でのまとめ
別ブログの記事を書くにあたり、佐々木氏の本から私が理解したこと、エッセンスを書くとしたらどのようにしたらよいか迷ったのですが、各経典について、私なりに「大乗仏教における位置づけ」、「悟りに至るロジック」、「具体的な教え」という3つの項目に分けて整理して書いてみました(佐々木氏はこのような項目建てはしていません)。扱った経典は、佐々木氏の本から、「般若経」、「法華経」、「浄土教」、「華厳経」、「大乗涅槃経」を選びました。
3つの項目の趣旨は以下のとおりです。
「大乗仏教における位置づけ」というのはそのままの意味です。
「悟りに至るロジック」というのは仏教独特の仕組みです。仏教では、ブッダ(悟った人の意味)になるためには授記(先輩のブッダに会い、修行に励むことを誓い、頑張れよ、と励ましてもらうこと)が必要とされているのだそうですが、実際問題としてそう簡単にはブッダに会うことができませんので、その問題をどう解決したらよいか、ということです。経典ごとに異なる手法があり、これが、経典の性格を明確にする要素の一つかと思われます。
「具体的な教え」の項目では、各経典に書かれた教えのエッセンスをまとめてみました。
以上のようなまとめ方に興味がありましたら、私の他ブログの記事「自社訪問 虎の巻 大乗仏教の誕生と大乗経典の変遷」を御覧ください。